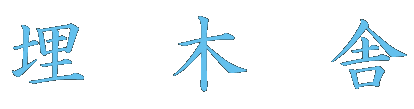さて、舎利弗は、十大弟子の筆頭としてお釈迦様から
「授記」 を受けています。授記とは、ゆくゆくは仏となるであろう証明のことです。さすがに最も頭の良いお弟子だけのことはありますが、 「大智
の舎利弗、なお信をもって能人となす」 という言葉もあります。これは日蓮にちれん
宗のご祈祷きとう などでしばしば唱えられるものですが、大智の舎利弗でさえ、信仰によってはじめて仏道に入りこと出来たという意味です。
仏教学者になるには、それ相応の学問が必要ですが、仏教徒になるには、学問は必ずしも必要ではありません。実際、大智の舎利仏と対照的に、弗弟子にには必ずしも学問的な知識が身につかない方もありました。
周梨槃特
しゃりはんどく (チューダパンタカ)
といわれるお弟子は、まさにそうした方でした。この方は、いわゆる知的障害者だったようです。このため、お釈迦様のむずかしい教えはいくら聞いても理解出来ませんでした。そこである時、お釈迦様から、
「お前はひたすら偈 げ を唱え、箒
ほうき を持って掃除をしなさい」 と命じられるのです。周梨槃特は命じられた通り
「塵 ちり を払い、垢
あか を除かん」 という短い言葉 (偈) を繰り返しながら、雨の日も風の日も、ただ黙々と掃除を続けました。そしてある時並み居る高弟を差し置き、忽然
こつぜん と悟られたのです。理屈では 「ひたすら心の垢を取り除いていたことを悟った」
などと解釈しますが、いずれにしても、この愚直なまでのひたむきさが、本質への近道であったのは間違いありません。この方は、悟りを開いたとお釈迦様より認められ、
「箒の聖者」 と呼ばれています。
悟りとは理屈ではありません。全身全霊で感じ取るものなのです。
大体、仏道修行をしようということでお寺に入りますと、どこでもお掃除が何より大切ということになります。仏様を拝むより、お掃除が先なのです。それも、のんべんだらりとただやっていてはダメなのです。私の師匠は
「最近の者は、壇に上がって拝むこと以外は、修行だと思っていないようだ」 と言われ、小僧時代、もともと怠なま
け者の私は、よくその杜撰ずさん
さを指摘されました。
私の師匠は大変ほ祈祷きとう
のきく人で、私も師匠のようにご祈祷中心でやりたいと思って弟子入りしたのですが、当の師匠は 「私は拝むことで祈祷の力がついたのではない。掃除をしたから出来るようになったのだ」
と、よく言っておりました。
どういうことかと尋ねると、師匠が本山にいたころ、雪の日に参詣者がお参りしやすいように、毎日ずっと雪かきして道をつくったというのです。何分山の上のお寺ですから、冬になると雪は毎日のようによく降ったとのことです。それで毎日毎日、雪かきをやっていたら、本尊様が喜んで力を下さったのだと言っておりました。
とかく修行といいますと、辛いことを自分に強いたり、あるいは観念的な精神集中に終始することに関心が置かれがちで、周囲の状況が見えないままにひた走る傾向がありますが、大乗仏教ではまず、周囲への思いやりの心を実践するということが、第一の修行となります。この心を本尊様が喜んで下さったということなのでしょう。
話しがそれましたが、そんなわけで舎利弗はたまたま智慧第一の人でしたが、仏道を学ぶには必ずしも利発である必要はなく
「信」 、つまり素直にそれを受け入れて、大切にすることが重要なのです。
ここで、舎利弗について少し捕捉しておきましょう。この方はしばしばお釈迦様の代わりに説法されたほどの智慧者で、同じ仏弟子である羅?羅らごら
の直接の指導者でもありました。梵語ではシャーリプトラといいます。婆羅門の出身で、目連とともに、もとは懐疑論者のサンジャの高弟でした。この時舎利弗には、すでに250人もの弟子がありましたが、お釈迦様の説法を聞き、その場で改宗したと言われています。この後、目連とともに250人の弟子を集団改宗させ、その足で弟子たちを引き連れ、お釈迦様の教団に移りました。このため、先師であったサンジャヤは悔しさで憤死したと伝えられています。
舎利弗は、すでに懐疑論自体に懐疑的になっていたのでしょう。そんな時にお釈迦様と出会い、すべてを信じないという立場を捨てて、あえて信じることを選びました。彼はこの時何か大きな手応えを得たに違いありません。それは、不毛な懐疑論とはまったく違う何かであったのでしょう。ちなみに、お釈迦様が舎利弗に寄せる信望はきわめて篤く、御釈迦様に先立って亡くなられた時には、普段はあまり感情を表に出されないお釈迦様でさえ、大いに嘆かれたと伝えられています。 |