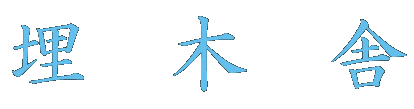つづく祝典の日々、ヴォルフガングは夢中になって豪華な催し物を楽しんだ。
宮廷での大晩餐会、仮面舞踏会、競馬、二輪馬車の競争、大音楽会、小音楽会、野外音楽会、芝居、見せ物小屋、人夫祭り、綱渡り、農家の娘百人の合同結婚式、市民のための公道に設けられた大宴会テーブル・・・・・。
ミラノ中が興奮状態におちいり、近隣の町や村や国から押しかけて来た見物人が町を走り回り、人を乗せすぎたバルコニーが落ち、それをまた見に見物人が押しかけ、そのめまぐるしさとそうぞうしさといったら、大変なものだった。
だがヴォルフガングには、そうした刺激がたまらなく快かった。
大任を果たしたあとの開放感、町中で話しかけられ、ほめられ、祝いを述べられることの嬉しさ。
それに比べてあのザルツブルクはなんと活気がなく、やぼったく、退屈なのだろう。
「パパ、ねえ、もうずっとここにいようよ。帰りたくないんだよ。帰らなければならないと思うと、ぼく頭が変になりそうだ」
父親が頭に練っている計画を知らないヴォルフガングは、たびたびそう言っては無言のレオポルトの顔を見上げるのだった。
まもなくレオポルトは留守宅の妻に、帰郷が少し遅れそうだと書き送った。
『体中にはげしいリューマチが起こって、わたしは二日ほど宿に閉じ籠もっています。ニワトコの花のお茶と黒色粉薬を飲んで、この病を追い払おうとしています』
つぎの手紙には、
『幸い病は治ったが、まだ出発が出来ないでいます。大公殿下がヴァレーゼの宮殿からお戻りになられたら、われわれとお話になりたいとのことです。わたしたちの当地滞在は、まだ十日以上のびるのは確実です』
またその次の手紙。
『わたしたちはまだ当地にいて、たぶんこの先一週間はここにとどまっているでしょう。なぜなら大公殿下は火曜にやっとヴァレーゼからお戻りになり、それからわたしたちと会う日をお決めになるからです』
親子は十一月三十日になっても、まだミラノにいた。故郷から、十月と十一月分の給料も停止されたと通知があったにもかかわらず、オペラ公演も祝典もとうの昔に終わって、何も無いミラノに留まり続けた。
実はレオポルトはフィルミアン伯爵をとおして、ある内密の交渉を行っていたのだ。伯爵の好意と力を頼ってのことだった。
「愚息を、フェルディナント大公殿下の宮廷音楽家に取り立てていただけないでしょうか。オーストリア皇子のもとで働くことが出来ましたならば、愚息にとりましてどれほどの栄誉となりましょう」
ハウスブルグ支配下のイタリアのどこかの理想的な宮廷。ヴォルフガングを雇わせるのに最適な場所として、レオポルトはマリア・テレージアの第三皇子、フェルディナントが治めるミラノの宮廷に白羽の矢を立てたのだった。 |