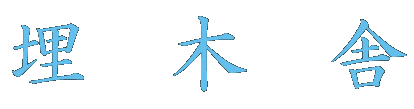つねにヴォルフガングの絶対的な後援者であるフィルミアン伯爵は、快く交渉を引き受けてくれた。
「この話しは大いに可能性があります。大公殿下も天才少年を、ご自分の宮廷につなぎとめておきたいというお気持を、強くお持ちのようですから」
十一月のはじめに、伯爵は大公にそのことを話した。大公は大変に乗り気で、実際にレオポルトとの間で行われた話し合いでも、
「余はそれを望む」 とはっきり述べた。
しかし、大公は最終的な決断を下せなかった。まだ十七歳の未成年であり、母マリア・レテージアの従順な息子である大公は
── 花嫁を選んでもらったのと同じように ── 神童を自分の宮廷に入れることに関しても、母親の了解を取らなければと考えたのだ。
そこで大公はウィーンに手紙を書き、その返事が来るまでは確答を避け、その間レオポルトは、訳が分からずに待たされていた。
しかし、これ以上休暇を伸ばすことは不可能だった。大司教宮廷での奏楽が始まる十二月の二週目までには、なんとしてでもザルツブルクに帰り着いていなければならない。
十二月に入ってすぐ、大公に別れの挨拶にあがった親子は大公から、
「今この場では君を宮廷音楽家に任命するのは無理だが、空席が出来た時には、真っ先に考えよう」
と約束された。
まだ母親からきちんと承諾をもらっていない大公にしてみれば、それが今の時点で示せる最高の好意だった。
親子は十二月五日にミラノを発ったが、レオポルトは後髪を引かれる思いだった。
──
空席が生じた時に、はたして大公殿下がヴォルガンフのことを思い出して下さるかどうかは、非常に疑わしい。ミラノを去ってしまえば、息子のことなどお忘れになることもあり得るのだ。
レオポルトの不吉な予感は、しかし別の形で当たっていた。
親子がブレンナー峠にかかろうという十二月十二日、ウィーンではマリア・テレージアが息子に次のような手紙をしたためていたのだ。
『あなたはあの若いザルツブルク人を自分のために雇おうとしていますが、わたしはなぜだか理解出来ませんし、あなたが本気で作曲家のような無用の人物を必要としているとは信じられません。けれどあなたがどうしてもというのなら、わたしは邪魔はしたくないのです。あなたは無用な人間を雇わないように、そして決してそうした人たちに肩書きなど与えないように。乞食のように世の中を渡り歩いているそのような人間は、奉公人たちに悪い影響を及ぼすことになり、宮廷のためになりません。そのうえ、彼は大家族です』
親子は希望と不安の間を揺れ動きながら、十二月十五日にザルツブルクに帰り着いた。
その翌日、親子に寛大だった大司教シュラッテンバッハ伯爵が、急な病のために七十四歳の命を閉じた。
|