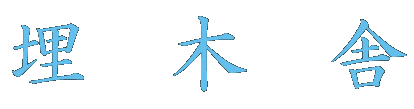その年の暮れ、一七七〇年十二月二十六日、ミラノのドゥカーレ劇場は少年ノーツァルトのオペラ
《ポントの王ミトリダーテ》 の初演の幕をあけた。
オペラ作曲家としてのヴォルフガングのイタリア・デビューだった。
ここまでこぎつけるのは、辣腕政治家フィルミアン伯爵の後援をもってしても、容易なことではなかった。
今度相手にしなくてはならないのは、伯爵の息がかかった貴族たちではなく、歌手や劇場関係者や職業音楽家である。そうした人たちにとって、ヴォルフガングは
「かわいい天才少年」 ではなく 「強力なライヴァル」 だった。
もともとこの世界には陰謀が渦巻いている。
少年の出現によって仕事を減らされたり、奪われたりするのを恐れた人々は、束になってヴォルフガングの足をすくおうとした。
「こんなに幼い、しかもドイツの少年がイタリア語のオペラを書けるわけがない」
「あの子は確かにクラヴィアの腕は優れているが、オペラの作曲は別物だ。劇場に必要なニュアンスをドイツの小僧っ子が理解するのは不可能だ」
「あの子が書く音楽は、オーケストラで演奏出来るような代物じゃない」
親子がミラノに着いてみれば、巷にはもう、少年のオペラはツギハギだらけだという噂が広まっていた。
「おかしいね、だってぼくはまだ、レシタティーポ
(オペラや宗教作品などで、歌手がストーリーや状況の説明のため歌うように語る部分) とアリアを数曲しか書いていないのに」
「そう。こうした妨害は、われえあれはもう三年前にウィーンで体験済みだ」
その時のことを思い出すと、レオポルトの腹は煮えくりかえった。
「あの時も、お若い皇帝ヨーゼフⅡ世陛下じきじきのご依頼であったのにもかかわらず、おまえのオペラ
《見てくれの馬鹿娘》 はグルック (十八世紀最大のオペラ作曲家) 一派の妨害にあって上演されなかった。まず、台本書きがギリギリまで内容を変更しておまえに書かせまいとした。それから、グルックにそそのかされた歌手が
『こんなアリアは歌えない』 と騒ぎ出し、オーケストラは十二になりたての小わっぱに指揮などされてたまるか、といった調子だった。あげくのはてには、このオペラは子どもではなく父親が作ったものだ、と言い広める始末だ。おまえがオペラを書いたという事実を、連中はよってたかって隠そうとしたのだ」
「おまえもその時にはっきりと知っただろう。人間は才能を持たなければ無事だが、持っていればその程度に応じて嫉み、そねみに追い回されるということを。この世の中は、つかみあいの喧嘩をしなければ、渡って行けないのだ」
「うん」
「われわれはあの時ウィーンで、四ヶ月も引き回された挙句たいへんな金を浪費して、結局得られたのは
『オペラの上演は妨害なしには行われない』 という教訓だけだった。今、このミラノで全く同じことが行われようとしているが、有り難いことにプリマ・ドンナのベルナスコーニ嬢は、おなえの強力な味方になってくれている。有名な作曲家のランプニャーニさんも同様だ。それに写譜
(楽譜を手で写すとること) の人たちもこのオペラに夢中になっている。これは大切なことだよ。写譜屋が敵に回ったら、わざと書き違えたり、仕事を遅くしたり、どんな妨害だって出来るのだから」
「パパ、今度はぼくたち、うまく切り抜けられるよね」
「もちろんだ。この国に来てから、神さまはいつだってわれわれの味方をして下さった。今度も手を取って障害を乗り越えさせて下さるさ」
劇場監督カスティリオーネ伯爵が用意してくれた宿は、ドゥカーレ劇場の近くにあって、観劇にも貴族の訪問にも便利だったが、ヴォルフガングはほとんど一歩も外に出ず、真剣にオペラの作曲に取り組んだ。
夜眠くなるまで作曲のペンを手から離さない少年は、父親の家族への手紙の追伸に、
『弟ヴォルフガング・モーツァルト。その指は書いてばかりいて、くたびれ、くたびれ、くたびれ、くたびれています』
と記すのだった。
|