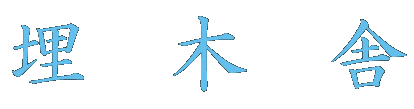| 栄光と賞賛の日々
(七) | フィレンツェ。
ここに宛てたフィルミアン伯爵の推薦状は、ローゼンベルク伯爵邸の扉を開かせた。ローゼンベルク伯爵はすぐさま親子を、トスカーナ大公レオポルトの宮廷にいるサルヴィアーティ公爵のもとにいかせ、大公の侍従長を勤める公爵は、すぐに親子を大公に引き合わせた。
一介の音楽家ならば、一月も待たされるであろう謁見
が、その日のうちになされたのである。
さらに幸運なことに、マリア・テレージアの二番目の息子であるレオポルト大公は、八年前シェーンブルン宮殿で会ったヴォルフガングのことをよく覚えていた。
「あの時君は本当に可愛かったね。何歳だったのかな?」
「六歳です、殿下」
「そう、余はたしか十五歳だった。まことによくクラヴィアを弾く幼児がウイーンに来ていると言うので、宮廷の者も大騒ぎしていた」
「そのように覚えていただけることは光栄です、殿下」
「まだ覚えているぞ。君は大広間ですべって転んだ時、助け起こした妹のマリー・アントワネットに、
『おとなになったらぼくのお嫁さんにしてあげる』 と言ったね。だが妹は間もなく、フランス皇子と結婚することになっている。気の毒なことをしたな」
「殿下、おからかいにならないで下さい」
「ところが、あの時一緒に弾いた君の姉君、君はナンネルと呼んでいましたね。あの方は今どうしていますか?
元気ですか?」
大公の宮廷の人々は、大公がヴォルフガングに特別な好意を示すのを見て、競い合って親子を歓待した。
翌日には大公の離宮で大音楽会が催され、ヴォルフガングは宮廷楽長ナルディーニの伴奏で、自作のクラヴィア曲を何曲も弾いたうえ、自称
「イタリアの対位法作家」 というニヴィッレ侯爵が出す難解なフーガを、それこそ鼻歌まじりに弾きとばして、居並ぶ人々の度肝を抜いた。
例によって例にごとくまき起こる賞賛のうずの外に立ち、レオポルトは同業のヴァイオリニストであるナルディーニと情報を交換していた。
「このストカーナの宮廷は音楽家にとって、たいそう働きやすいところです」
ナルディーニはフィレンツエの音楽状況をこう説明した。
「レオポルト大公は多くの優秀な音楽家を抱えて、彼らを優遇していますし、貴族の方々も音楽に詳しいので働き甲斐があります。この宮廷の芸術的レヴェルはイタリア一、といっていいかも知れません」
「なるほど」
「確かにそのようにお見受けしますな」 「うらやましいお話で」
レオポルトは相づちを打ちながら、こころにムクムクと野望がわき起こるのを抑えられなかった。
──がヴォルフガングが勤めるとしたら、このような宮廷がいいのだ。フィレンツエの町は美しく、大公のおぼえもめでたく、音楽家は大切にされている。ここで生活が出来たらどんなにいいだろう!
今回のイタリア旅行の最大の目的
── ほかの二つの目的、がヴォルフガングをイタリア・オペラの作曲家にすることと、 「音楽の神さま」 マルティーニ神父について学ばせることは出来たが、残るこれだけは絶対に言えない秘密の大目的
── それはがヴォルフガングをイタリアのどこかの宮廷に雇ってもらうことだった。
誰が見ても 「神童」 としか思えないこの特別な存在がおさまるには、ザルツブルクの宮廷はあまりにも小さく、あまりにもレヴェルが低い。大司教シュラッテンバッハ伯爵は、息子を大切にはして下さるが、どうにも全体的な器が小さすぎるし、みすぼらしすぎるのだ。この
「音楽の祖国」 の理想的な宮廷にこそ、息子は定職を得ておさまるべきなのだ。
その候補地の一つとして、レオポルトはストカーナ大公の宮廷を心に刻み込んだのだった。 |
|
|