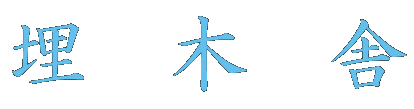九月にワルシャワへ戻ると、エルスネルが校長を務めるワルシャワ高等音楽学校に入学した。
ほかの生徒とはあきらかにかけ離れた才能を示す存在であったのは確かだが、ショパンのほかにトマシュ・ナポレオン・ニデツキら音楽家として足跡を残す生徒もいた。また、後にパリでの生活の中でショパンの作曲活動を写譜などして支えるユリアン・フォンタナも同級生にいた。
ショパンは週に三回二時間づつエルスネルから対位法と作曲のレッスンを受け、入学したこの年には
<マズルカ風ロンド> ヘ長調・作品五や <三つのエコセーズ> 作品七二の三、 <ポロネーズ> 変ロ短調、 <マズルカ>
ト長調、 <マズルカ> 変ロ長調などが次々に作られていった。
音楽学校の生徒として目覚しい成果を示し、さらに <ソナタ> ハ短調・作品四を手がけながら、ショパンの興味は音楽だけのとどまらず、大学で文学と歴史の講義も受けていた。そこで出会ったカジミエシュ・ブロジンスキの講義は、ショパンの知識欲を刺激した。ブロジンスキは、ロマン主義について説き、創造は
「霊感によるもの」 だとした。感情のおもむくままに創造にとりかかり、そこから冷酷なさばき手となって感情を遠ざけ、形式を与え推敲
する、それが芸術創造というものだ。熱くこのようなことを語るブロジンスキの講義に、ショパンは熱心に耳を傾けていた。
エルスネルが見守る中、ショパンの才能を物語る作品が二曲、作られた。
<ソナタ> ハ短調・作品四と、 <マルズカ風ロンド> ヘ長調・作品五だ。
<ソナタ> 第一番にはエルスネルに学ぶ生徒らしい気負いがある。曲はエルスネルに献呈されたが、出版はショパンの死後二年たった1851年だ。出版がそれほど遅れたのには理由があった。第二楽章や第三楽章にはショパンらしい美しい旋律、とくに第三楽章はノクターンの抒情性に通じるものがあるのだが、古典的形式に精通していた師の教えの成果を発揮しようと躍起やっき
になっていて、どことなくぎこちなく、ショパンらしい繊細さと独創性に欠けていると考えられ、評判は芳かんば
しくなかったからだ。
ここに見られるのは 「学ぶ」 ショパンで、その一方で、学ぶ必要などなく独創性を発揮するショパンがいる。それが <マズルカ風ロンド>
だ。この作品は <ソナタ> 第一番より二年ほど前に作られたのだが、 <ソナタ> で感じられる躊躇ちゅうちょ
もごこちなさもない。ショパンが慣れ親しんでいたマズルカのリズムと、リディア調による哀愁のある旋律が聞こえて来る。彼が終生手放すことなく、素材として何度も戻っていったポーランド民族音楽が、ショパンの手によって和声的にも旋律的にも複雑にされ、芸術音楽の域に達している。
このようなショパンの様子をエルスネルは見守っていた。ソナタ大規模な古典的形式がまだ手に余るようなことはあっても、やがて自分のものとするだろう。ピアノという楽器から離れないかぎり、ショパンの才能は確かな手ごたえを示しながら、実り豊かに作品を生み出す、そうエルスネルは確信していたに違いない。だからショパンに、学生の習作としてピアノ。ソナタの作曲はさせても、ほかの生徒に対してのように、オーケストラ作品作曲を必修だと無理強じ
いしようとはしなかった。オーケストラを使うのならば、ピアノをこそ加えた方がいい、ショパンの才能にはピアノが必要であることをエルスネル自身が誰よりの知っていた。
そこに生まれたのが、
<モーツアルトのオペラ 「ドン・ジョヴァンニ」 のアリア <ラ・チ・ダレム・ラ・マーノ> による変奏曲> 変ロ長調だ。この作品は、音楽学校在学中の1827年十七歳のときに作られ、たいへんな評判となった。
この作品を通して、ショパンの音楽学校時代の成果がさらに明らかないなる。ショパンは、オーケストラとピアノによる作品に、自分の才能の広がりを感じていた。この作品の成功から、その後三年ポーランドに滞在している間、オーケストラを背景にピアノがいかに美しく鳴り響き、歌えるかを追求することに夢中になっていく。
ポーランドを後にしてパリに到着する前の年1830年までに、ショパンはこの分野の作品を、ほかに
<ポーランド民謡による大幻想曲> イ長調、 <ロンド・ア・ラ。クロコヴィアク> 、そしてピアノ協奏曲二曲を含めた五曲も書き上げている。注目すべきことは、そのいずれにも民族的音楽的色彩が感じられることだ。ショパンらしいポーランド的音響をあふれさせる、とりわけ魅力的なピアノとオーケストラ作品が、二十歳になろうとするショパンの手から次々に生み出されていった。 |