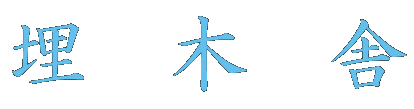|
2017/02/01 (水) | | 親友ティトゥス・ヴォイチェホフスキ | ショパンの外見は誰に似ているのだろうか。作曲家の中でショパンほど肖像画が多い人はいないように思われる。それぞれ異なった表情を見せるショパンではあるが、そのいずれにも、知的な気品、それでいてどこか頑なそうなそうな様子が見て取れる。生涯にわたって強いァで結ばれた姉のルドヴィカや、妹イザベラの目もショパンと似ている。深い光をたたえ、もの静かでありながら知的な想像力と創造性に富んでいて、それがジェラゾヴァ・ヴォラにあるショパンの生家に飾られた肖像画の両親の表情に共通するものであることがよくわかる。
両親や姉妹たちとの深い愛情に包まれたショパンが幼い頃から恵まれたものに、さらに友情を加えなければならない。父が経営する寄宿学校で出会った友人たちの中には、その死の1827年まで親友であったヤン・ビャウォブウォツキや、パリに出てからもショパンと親しく交際するユリアン・フォンタナがいる。しかしワルシャワ時代、とくに重要な人物はティトゥス・ヴォイチェホフスキだ。
ティトゥスはショパンより二歳年上だった。ショパンが十三歳のとき寄宿学校に入って来たのだが、同じようにジヴニーにピアノを習い、二人で四手連弾を楽しむことも多かった。
高等学校を卒業するとティテトゥスは自分の故郷であるワルシャワの東にあるポトゥジンに帰ってしまうが、その後ももっとも信頼すべき友人として手紙をたびたびやりとりし、ショパンがポトゥジンを訪ねることもあった。ティトゥスをひじょうに身近なものとして暮らしたショパンは、後世、研究家から同性愛ではないかとの指摘が出るほどに、
「ぼくの愛」 「ぼくの命」 といった呼びかけをしている。しかしショパンにそにょうな傾向はなく、多くの友人、知人がいながら、若きショパンが心から自分をさらけ出していたのは、ティテトゥスだったということを証明するものだ。音楽学校で出会った憧れの存在コンスタンツヤ・グワトコフスカもことを唯一打ち明けたのもティテトゥスにだったし、1830年にショパンがウィーンに行くことを決心したのも、ティトゥスが同行することを決めたからだった。 |
| | ベルリン旅行 | ショパンが外国にはじめて行く機会を得たのは1828年十八歳の時だ。ワルシャワの父の友人でベルリン・アカデミー出身の動物学者フェリクス・ヤロツキがベルリンの国際会議場に招待された時のことだ。初めての外国旅行、多くの音楽会、音楽家との知己を得られるかもしれないという期待で胸をふくらませて、ショパンはベルリンへの乗合馬車に乗り込んだ。
しかし期待どおりにはいかなかった。家族に宛てた手紙によると、1828九月十二日日曜日の午後に到着したのに、木曜日まで動物学会のほか何も見ていないとある。木曜日になってはじめて、ピアノ製造業者に会いに行き、翌日には楽譜出版社に行くことを告げている。結局、二週間ほどの滞在で、ウェーバーの
<魔弾の射手> 、チマローザの <秘密の結婚> などを見ただけで、ヘンデルのオラトリオ <聖セシリア> を聴いて、これこそ自分が理想と考える音楽だと書いており、ショパンが声楽の大規模作品に興味を抱いていたことがわかって興味深い。
オペラが好きなショパンは、ワルシャワでもロッシーニ、ドニゼッティ、ベッリーニ、モーツァルトなどのオペラ上演に必ず足を運んでいた。
1828年九月二十七日ベルリン最後の日、ワルシャワの家族に宛てた手紙によると、
「ここで見るべきものはすべて見ました」 とある。前日に見たオペラでプリマが歌った半音階が独特の魅力にあふれていたが、ドイツ語の発音がフラン語的で意味が違って聞こえることなど鋭く指摘している。しかし、音楽家としての成果は少なかった。
メンデルスゾーンやスポンティーニの姿を見かけながら近寄れないままに終わった。ワルシャワでももうすでに名の知れた音楽家だというのに、旅行中の一番の成果は出会った学者たちを描いたユーモラスなスケッチだった。 |
|
| | 『ショパン』 著:小阪
裕子 ヨリ | |