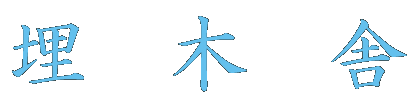橋上は、一来法師、筒井浄明などが、名乗り出たのをきっかけに、乱軍の模様をおびて来た。
五智院ノ但馬は、衆を相手に、奮戦していたが、橋桁の間から、宇治川へ墜ち、一来法師もまた、無数の矢を身に負いながら、戦い戦い、ついに斬り死にしたかに見える。
組み合って、ともに落ちるもあり、逃げんだれる勢のまま、もろとも、川へ落ちた人数も少なくない。
何しろ、橋桁の上では、兵量も自由に使えないし、騎馬も用をなさないので、討ちつ討たれるつを、随所に、くり返すのみであった。
「はて、いたずらに、こう暇
どっていては、なりますまい」
薩摩守忠度ただのり
は、知盛、重衡の駒わきへ、駒を寄せて、大願の敵を指さした。
「── 御覧ごろう
じあれ、あのうちには、宮の陣座も、頼政の姿も見えませぬ。かかるまに、宮は先へ落ち給えるものと思われる」
すると、重衡が言った。
「いやいや、平等院の唐橋からはし
をうしろに、一むらの松を楯たて
とし、夏柳の茂りを巡って、こなたへ弓を向けている一群こそ、宮や頼政のおる本陣ではないか」
知盛は、かぶとの眉廂まびさし
に小手をかざし、
「なんの、あれは頼政の子、仲綱、兼綱、そのほか渡辺党の一類よ・・・・。はて、これはまずいぞ。忠度殿のいうがごとく、敵に時をかせがれては」
と、馬の足掻あが
きにも、あせりを示した。
おりから川の水かさは、五月の降雨期以後も、雨がちであったので、少しも水量は減っていない。濁流、とうとうの相すがた
である。
知盛は、岸辺を洗う水鳴りと飛沫ひまつ
を眺めて無念そうに、行きつ戻りつしていた。
── 急に、兵馬を渡す手だてもないとすれば、淀まで退いて御牧みまき
村を迂回するか、河内路をとって、奈良へ入るしかない。
(ばかな。そんな間ま
ぬるい策を取っている暇があるものか)
自分の、常識をあざ笑う。
しかし、常識を破る試案もない。
── と、彼の眉毛のビリビリうごく気配を見て、上総介忠清の子、足利又太郎忠綱が、
「これしきの流れ、馬筏うまいかだ
を組み渡せば、渡れぬことはありますまい」
と、進言した。
足利又太郎は、まだ十七歳の小冠者なので、知盛は、余り意にかけない様子だったが、ふと、
「馬筏とは、どうすることぞ」
と、訊ねた。
又太郎は、得意になって、
「われらの住む武蔵、上野こうずけ
の国ざかいに、利根川と申す大河の候う。川幅といえば、この宇治川の三倍も候うべきか」
と、得意そうに語り出した。
「先年、秩父党と足利党とのあらそいに、秩父勢のため、みな、船を壊こぼ
たれ、いかにせんと、思案のおり、味方の新田義重が励ますようには。── 坂東武者の習いもあるぞ、敵を見ながら、川の淵瀬ふちせ
にへだてられ、むなしく、空弦からづる
そろえてよいものか ── と、すなわち、馬筏組んで、いちどに押し渡りまいた。その仕様しよう
は、我らに先手をゆるし給わば、宇治川の先を切って、お見せ仕りましょう」
「おもしろい」
知盛は、鞍くら
つぼをたたいて、
「足利の手勢に習い、われらも馬筏を組んで流れを渡ろうぞ。── 続けや、殿輩とのばら
」
と、後ろの味方へ呼ばわった。
上総介忠清、その子足利又太郎を先頭に、まず東国の大番武者が、ざんぶ、ざんぶ、馬を川へ進め出した。生方うぶかた
次郎、桐生六郎、田中宗太、佐貫広綱、小野寺太郎、山上、深須、大室、大胡おおご
、那波などという坂東各地の郷名さとな
を名乗る輩やから だった。
馬には泳ぐ性能がある。水にも激する性格がある。水馬の術は、調和である、そう二つの特性を、巧みに騎御きぎょ
してゆくだけのことに過ぎない。
で、水馬に練達している又太郎の姿は、奔流に流されながらも、水と遊び、流れにまかせ、いかにも安々と、渡って行くように見えた。
「──
やよ人びと。先を争うな、馬組み乱すな。弱き馬は、下手しもて
に庇かば い、強き馬をば、上手かみて
になせ」
と、彼らは、うしろに続く面々へ、たえず心得を告げ渡していた。
「── 流れに押されて下がる者には、弓ゆみ
の弭はず へ取りつかせよ。手に手を取り組み、肩に肩を並べ、馬のかしらが沈むと見たら、手綱かろく引きあげよ。強く引いて、馬を撓ため
めころすな。鞍壺くらつぼ 、しかと乗りさだめ、あぶみは、たしかに踏めや。敵は射るとも、相引きすな。矢防ぎには、兜かぶと
のしころを傾けよ」
一陣、二陣、三陣とわかれ、こうして、六波羅勢は、西岸へ迫り、すでに岸辺にとりつけかけた。
当然、宮方は色めき立ち、弦つる
をそろえて射出したが、およそ持ち矢にも、予備の矢にも、限度がある。
それに、敵勢は十倍の量だし、橋下を防いでいるまには、橋上の桁けた
を歩兵が渡ってくる。
「これまでぞ」
と、梨ノ木の仲綱は、弟の兼綱へ向って言った。
「平等院の内へ退き、一緒に死のうぞ。西大門、北大門を閉め、もう一と防ぎしたうえで」
|