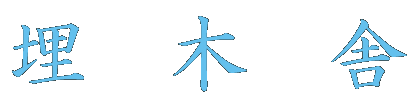二つの対立は、一つにならなかった。一つになるかと見えながら、陰に陽に、機微な動きを作用しながら、数日の間に、一山は、またもとの二つに、はっきり割れた。
初め。
外部から来た頼政一族の武力を見、それに怖
れて、ひたと、統一されたかに見えたが、頼政の率いる武者も、六、七十騎にすぎないと見透かしてから、
「あのような老武者や、古物をかき寄せたような廃すた
れた源氏の小勢で、何が出来よう」
と、いう軽蔑けいべつ
がきざし、宮の行動を批判したり、仏者は仏道の行者たるべきで、武略や戦闘に関るなという論議も出、前よりも反戦的に、いや、もっと露骨に平家支持の傾向が高まっていた。
すると、二十五日のこと。
一来法師と五智院ノ但馬が、法輪院御所へ来て、
「三位殿、おわすか」
と、事ありげに、対談を求めた。
そう二人から、何事か、密語を聞いた頼政は、彼らが帰るとすぐ、宮のおん前へ出た。
「昨夜、法親王には、一如坊真海、法印禅智などに、唆そそのか
され給い、かつは大勢の弟子法師に取り囲まれ、否やを宣の
らせ給うこともならず、闇夜あんや
にまぎれ、六波羅へ落ち行かれた由にございまする」
「なに、弟が、六波羅へ、奔はし
ったとか」
宮は、愕然がくぜん
と、叫ばれて、
「まろが身を、この兄を、敵の六波羅へ売る心よな」
と、ののしられた。
「いえ、いえ。御本心ではないせしょう。いかように思し召しあろうとも、この中では、御無理もありません。囲?いによう
する輩やから の妄言もうげん
と武力に囲まれ、御意志は無視され、法親王の尊位を、逆に、利用せんとする者に、みすみす、お力も及ばず、身を任せ給うたものと思われまする」
「頼政・・・・」
と、宮は落涙をお見せになって ── 「恃たの
むは、おことのみぞ」 と、言われた。
頼政は、ひれ伏した。── 何かふと、罪深い気がして、胸が傷いた
まずにいられない。
悪日あくび
であった、その二十五日は。
たれともなくまた、いい噪さわ
ぎ出した。
「叡山へ、院宣が降った」
「三井寺討てとの院宣よ」
「すでに、山門の僉議せんぎ
は、新院高倉の御使を奉じ、大挙して、これへ襲よ
せて来るそうな」
あらしのような動揺である。
加うるに、六波羅の軍勢は、宗盛、教盛、維盛、清宗以下、千余騎、如意越え、逢坂おうさか
越えの二道から、逆落としにこれへかかって来るだろうと、物見は急迫を告げて来た。
頼政は、宮のおん前にぬがずいて、静かに、おすすめした。
「奈良へ参りましょう。南都こそ君の御陣所を置かるべき所でした。三井寺と事ちがい、興福寺大衆と平家とは、倶とも
に天を戴かずとしている宿怨しゅくえん
の間がらです。また藤原氏歴代の祖廟そびょう
の地、かしこへお遷うつ りあって、しばらく平家をあしらううちには、諸国の源氏が、蜂起ほうき
して立つこと、疑うまでもありません」
「・・・・が、頼政、ここをいつ立ち出るか」
「かくなっては、一刻をも争いまする、今宵のうちにも」
「え、今宵とな」
宮は、ふるえをお隠しになっているが、お唇くち
の色は、蔽おお いようもない。
「それも、二心なき者のみ選んで、風の如く、お立ち退の
き遊ばさねば、寺中の怪しき気振けぶ
りの者どもが、追い撃ちをかけて参るは必定と存じまする。・・・・が、頼政あるからには、ゆめ、み心安う思し召せ。何条、不逞な悪法師ばらに、奇功を得させましょうや」
灰色の翁髯おきなひげ
を動かして、ほそぼそと説く頼政の低い声音こわね
ではあった。しかし、宮は、彼の姿を前に見ておられると、常に、その間だけは、御自身までが、静かになった。なぜか、安心感にくるまれて、彼の説には、遅疑もなく、おうなずきになるのであった。 |