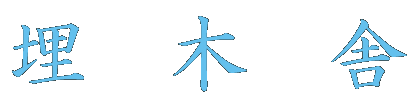宮は、笛をお唇
にあてた。お好きな道とて、笛を取ると。お顔まで、何か、きれいに澄んで、気高けだか
く見えた。
鶴丸は、退さ
がって、草の中にかしこまり、宮の吹き給う笛に、首を垂れ聞き入った。
夕雲の流紋は、飽かずに、宇宙の殿堂へ壁画を描いては溶かしてゆく。地上の草の穂、岩のかど、宮のお姿までが、茜染あかねぞ
めに隈くま どられ、あたりは妖あや
しい紫靄むらさきもや に暮れかけた。
「・・・・おや」
ふと、笛の音が曇ったので、鶴丸は首を上げ、そして、宮の双そう
の頬に、白い涙のすじを仰ぐと、彼も泣きたそうな眼をしばたいた。
しかし、笛の譜ふ
は、宮のお胸のものを、みな吹き放ってゆくようだった。そのお眸も笛の律呂りつりょ
も、ふたたび、生き生きと、よみがえっていた。生命の歓びを強調する感興だけがあった。
急に、草も踊り、木々も奏かな
で、命のある物は、みな笛につれて、そよぎ始めた。すると、宮のうしろに見えた山苺やまいちご
の白い花の枝から、一匹の小蛇こへび
がチロと鎌首かまくび をもたげほかの枝へ移ろうとしていた。
「あっ、蝮まむし
が」
鶴丸は、思わず、身をはね起こした。
蛇と聞くだけでも、すぐお顔色を変えるほど、宮は蛇がおきらいなのだ。鶴丸はそのため、よけいに大声を出してしまったのだが、果たして、宮は、跳と
び退の きざま、おん手の笛で、左の袖あたりを、びゅっと、夢中で打ち払った。
カサッと、何かが鳴っただけで、もう小蛇は、どこにも見えない。
宮のお手には、小枝さえだ
の笛の折れたのが、寸短に、残っていた。
「ああ。・・・・これも折れた。秘蔵の笛とも、はや別れかや。・・・・鶴丸、帰ろう」
その夜から、宮は、悪寒さむけ
を訴えて、御寝ぎょし につかれた。しきりに薬湯やくとう
などをお飲みになったが、微熱は下がらない。鶴丸は、宿直とのい
の夜半、宮のうわ言を、幾たびとなく耳にした。
二十二日の宵である、宮は突然、御枕を蹴け
って、起き出られた。八条女院の内に仕えている蔵人仲家、仲光の父子が、如意ヶ嶽を越え、宮を慕って、ここへ落ちて来たからである。
「今宵こそは、頼政以下、一族、田辺党の面々も、わが家をわが手で焼き捨て、洛中よりこれへ馳せ参りましょう。──
手はずはこうぞと、兼綱殿の密使を受け、われら父子も、即刻、女院へ内々お暇を告げ、都を脱けて参りました」
八条蔵人仲家は、木曾冠者義仲の兄にあたる者。宮をお力づけようとしてか、こうも語った。
「み気色を仰ぐに、おん窶やつ
れが拝されまする。しかし、もうお心づよく思し召せ。女院の蔭には、池頼盛殿もあり、奈良は、唯一のお味方。かつは、令旨をお伝えに急いだ十郎行家殿にも、つぎつぎ、所在の源氏に、呼びかけておりましょう。──
そのうえにも今、頼政殿が、親しく輔佐し奉るからには」
宮は、うなずかれた。頼政こそ、今はお心の支柱である。どれほど、彼を見る日の待ち遠しかったことか。
霧小雨の中もいとわず、宮は、仲家父子を伴い、山の尾根に佇たたず
まれた。すでに真夜中近い。近衛河原か梨ノ木辺りか洛東の空が、赤くなった。霧の海に、淡紅色の巨大な牡丹ぼたん
が開いているようにしかそれは見えない、それ以外は何もない霧だけだった。けれど、宮は眼ま
じろぎもせずながめておられた。 |