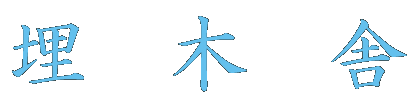うしろを振り向いては、宮は、
「鶴丸、供をして来たか」
「はい、どこへいらっしゃいます」
「鬱々
としてならぬゆえ、心を放ちに」
「げにも、高きに登ると、心が晴れまする。なんとよい遠方此方おちこち
のながめでしょう」
「・・・・たれだ、まだ後から来る人びとの跫音は」
「四時交代で、君の御身辺を守護している三井寺法師でございます」
「尾つ
いて来るなと申せ。せっかく、山路を歩いて、ひとり心をなだめようと思うて出たのに、僧兵どもの長柄や薙刀なぎなた
にぞろぞろつきまとわらてはかなわぬ」
「戻ってもらいましょう、御諚ごじょう
なればと、告げて」
鶴丸は、後へ降りて行った。
それきり、なかなか引っ返して来ない。宮は先へ行かれたが、また佇たたず
んで、彼の姿をお待ちになった。
すると下から鶴丸は見えたが、その鶴丸など眼中にもなく、数名の荒法師たちも、彼と一緒に追いついて来た。
宮は、むっとなされたとみえ、
「用はない、法師どもは帰れ」
と、しかった。
けれど、法師たちは、従う色もない。
「御諚には候えど、君に万一のことでもあっては、われらの勤めに欠けまする。上僧の厳命でもおざれば」
「上僧の命は奉じても、まろの意には従えぬと申すか」
宮はついに、おん眉に怒気を発して一喝いっかつ
された。押売りの忠義立ても、それには、二の足を踏み、彼らは、口ごたえの代りに、何かぶつぶつ言いながら、基の道へ帰って行った。
「僭上せんじょう
な・・・・」 と、宮は、余憤のつぶやきを、法師どもの後ろ姿へもらして 「── 付け人びと
は法親王の方だけかと思えば、まろの身にまで、小うるさい見張りをつけておくとみゆる。眼の前では、君の宮のと、いたずらに、敬礼きょうらい
のみはするが、じつは、まろの身を木偶でく
か案山子かかし のように心得ておるのだ。──
どうして、このように、世は虚偽に満ちているのか」
鶴丸の眼は、心配そうに、宮のみけしきを仰いでいた。
夜もお寝やす
みになれないらしい宮のここ幾日かを、この侍童 (小姓) は宿直とのい
して知っている。けれどこんな時に言うべき言葉が彼にはつかめなかった。彼は、せいいっぱいな気持で、宮のお心をほかの視界へ紛まぎ
らそうと努めた。
「── あれ、御覧ごろう
じませ、たくさんな足軽 (平時の雑役夫、戦時の雑兵) どもが、逢坂口おうさかぐち
の関や、四の宮の小関のそばに、堀を切ったり、柵さく
を結ったり、蟻あり のように、いくさ支度をしております」
つりこまれて、宮にも、お眸を、はるかになされた。
大関小関の戦備だけではない。湖畔の方にも、土塁や柵を設営している人群れが見える。櫓やぐら
が組まれ、楯たて をならべ、いつでもと、敵を迎え撃つ準備はなっているのだった。
「僧綱らのうち、たれとたれとが、煮えきらぬ態度をとっておるのか。事実は、このように、もう合戦へと、進んでおるのに」
宮は、いささか、み気色を持ち直した。お耳も色が冷さ
めるのと一緒に、ふたたび、山路の草を踏みしだいて歩み出し、やがて、ころあいな岩へお腰を下ろされた。
比叡つづきの峰々や、長等山ながらやま
の冷たい風が、湖を越えて、三上山と伊吹の間を吹きぬけて行く。
琵琶の水は、いちめんに、さざ波立ち、竹生島が、人を恋う孤独の寡婦かふ
みたいに、はるかであった。
「もう、源氏は島にもおるまい」
十郎行家から聞かされていた何かを思い出されたらしい。じっと、ながめておいでになる。まるでうつろかのような顔つきだが、そうしながらも、手の指は、笛袋の笛を取り出しておられた。 |