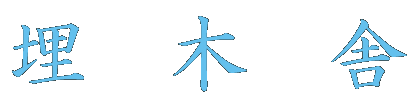夜半近く、暗い霧雨が、降るともなく降ってきた。
六波羅広場の兵馬は、約三百余騎しか残っていない。大部隊は、先に、奈良大衆の北上に備え、その方面へ出て行った。
「はてなあ、源三位頼政らの、渡辺党はまだ来ぬか」
病み上がりの知盛
は、この霧雨に濡れ、寒気さむけ
に襲われているらしい。ひた兜かぶと
の下に、青白い顔を埋め、卯う
の花はな おどしの鎧よろい
姿を、青毛の駒において、陣列の間を、往きつ戻りつしながら、
「のう重衡しげひら
、ちとおかしいではないか」
「と、うしろへ言った。
知盛は兄、重盛は弟、五つ違いの公達きんだち
である。
いうまでもなく、清盛の子たちだ。
「おかしいとは、兄君、何が・・・・」
「子ね
の刻は、すぎておる。しかるに、頼政一族が見えんとは」
「そう申せば、源大夫兼綱も来ておりませぬな」
「老いぼれの頼政はともあれ、屈強な渡辺党の輩やから
も、たれ一人、馳せつけておらぬとは心得ぬ。── たれぞあるか、一鞭ひとむち
あてて、近衛河原の様子を見て来い」
病の克か
とうと努めているのだが、知盛の声の底には疳気かんき
があった。
しかし、頼政の遅参を、不審と、すぐ考えたのも、病人のとがった感覚であったかもしれない。
本来なら、この三百余騎も、もう三井寺攻めに、発向している刻限なのだ。それをなお、こうしていたのは、西八条から
「── 出陣を待て」 と、今しがた、急使を受けたからである。
南都の上洛だけでも、その備えに、大軍を向けてあるのに、またまた叡山に動揺がみえ、三井寺と呼応して、山門大衆が、洛中へなだれ入るかも知れないという予測が西坂本の物見から、真夜中、告げて来たからだった。
清盛は、この夜、枕にもついていない。
常の法衣だが、下は武装していた。西八条いっぱいに、燭しょく
を照らしつらね、大庭には、かがり火を焚た
かせ、中門廊の陣座にあって、刻々の報を聞き、またつぎつぎに、指令を発していた。
幼帝安德の行幸を請うて、お座所を、池大納言頼盛の八条亭に移し参らせたのも、この夜である。
新院高倉にも、同様、御避難を仰いだ。
|