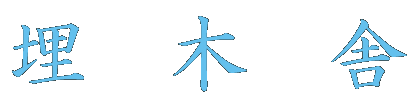頼政はそのとき、陣触れの使者を前に、作法どうりな礼をして答えた。
「このように老い朽ちた身もお忘れなく、非常の陣に、召しを給わったのは、老い木に花のよろこびです。わずかには候えど、家の子郎党をも触れ集め、時刻までには馳
せ参りまする。御披露、よろしきように」
彼は、みじんも、あわてはしない。
十五日夜から、二十一日の今夜まで、六日が間に、彼の心は、充分な備えを蓄えていた。どういう変へん
にも、応ずる構えは出来ていた。
「── 来たか」
と、思っただけである。
郎従の唱となう
は、とたんに、見えなくなった。
使者の駒音を聞くやいなや、唱は、裏門からどこかえ走り出して行った。
子ノ刻。まだ、時間のゆとりは、半夜もある。
頼政は、下部にいいつけ、夕餉ゆうげ
を食べはじめた。
箸をとりながら、彼はふと、
「わしは、鵺ぬえ
か。まるで鵺のような」
と、自分で自分のあり方を、奇異に思った。
歴史の古い、そして日常、陽ひ
も余り映さ さない大内裏には、よく雨の夜などに語られる話がある。
「鵺ぬえ 」 という怪獣は、顔は猿、手足は虎、尾は蛇の形をし、黒雲の下りる夜、殿上の大屋根を翔か
けるという。
主上やお后の御悩ぎょのう
で、加持かじ 祈祷きとう
の効き き目もないのは、鵺のたたりで、歴朝、悩ませ給うた生き物だが、堀河の朝ちょう
に、猪い ノ早太はやた
なる滝口の勇士つわもの がいて、ついに強弓にかけて、射たという。
そんな他愛のない話なのである。けれど、他愛のない中に、何か諷ふう
しているものがある。後宮こうきゅう
の脂粉の中にも、廟堂びょうどう
の大官中にも、歴代、鵺は皇居に巣くい、主上を悩ませたり、善良な諸民をおののかせていたといえなくもない。
ふと、頼政は、自分もその類たぐい
ではないかと、自嘲したのである。
この素知らぬ顔つき、腹の中、似てはいよう。けれど、武門以外に、祟りをなした覚えはない。天地に恥じるやましさはない
「ただひとり、この期ご
に、すまぬ心地のするお人と申せば」
彼は箸をおいて、心を、西八条の方へ向けた。
相国清盛を思い出すとき、彼は、涙なきを得ない。ひそかな、良心を抱いて、
「今生は、ゆるし給え。地獄においては、いかなる面罵めんば
も、お受け申そうほどに」
と、慙愧に打たれた。
平治の戦いに、同族の源義朝を見かぎり、平家へ寝返った自分を、無条件に、容い
れたのも、清盛である。
年久しく、兵庫寮や衛府の貧しい一武官におかれたまま、人には忘れられていた自分を、昇殿しょうでん
の資格に取り立ててくれたのも、彼であり、また、老後の大病のさい 「三位」 を奏請してくれたのも彼である。その温情は、一再にとどまらない。
ああいう寛大と、あたたかい心の持ち主を、人生七十七年のうちで、頼政は、清盛以外に知らないほどである。
「もし頼政が、武門の人間でなくば。そして、源氏の系流でないならば・・・・ああ、わしは歌よみの頼政法師として、死ねたであろうに」
と、心から思う。
──
あんな、抜け目だらけな、寛大の度も越えた好人物の入道殿に、どうして弓が引けようか、本来、叛そむ
けるものではない。それを自分は、彼の弱点と見すかし、能うかぎり、利用してきた。人間の善意を、善意でこたえず、逆に用いた。 |