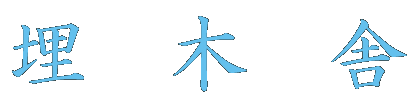その後の頼政ほど、複雑な立場にあった人はあるまい。月はここにも白々と更
けていたが、彼の胸を去来する不安やら、あすの思案は、疾風雲はやてぐも
のようだったろう
すき漏る月影のほか、頼政の寝間は、暗かった。時おり、ゼイゼイ痰たん
のからむような咳声しわぶき がそこから聞こえる。宵すぎると、館は妻戸つまど
遣戸やりど を閉た
てさせ、ふだんのように、しいんとしたが、眠りつけるはずもない。
長い長い、みじかい夜だった。
すると、人の忍び足が、みしりと、寝間の外で止まり、たれか、そこへかがまる気配がした。
「唱となう
か」
寝返り打つと、
「さ候う。ただ今、もどりまいりてござりまする」
と、外の者は、小声で答えた。
頼政は起き直った。しかし唱に、入れとは言わない。灯をともす様子もない。ただ行儀をかえて、そのまま。内から訊たず
ね出した。
「唱。・・・・宮の御安否は」
「まずは、おつつがなく」
「おつつがなくとは、三井寺へ落ち入らせ給うたことか」
「白河、如意にょい
の山路を越えさせられて」
「そうか・・・・」
大きな息が、壁の内に、はっきり聞こえた。胸なでおろしたように、しばらく声もない。
「唱」
「はい」
「してまた、御所のおんあとは」
「見届けえたところによりますと、宮の侍、信連が、あとに残って、よく戦い申してござりまする」
「斬り死にしたか、信連は」
「いや、搦から
め捕と られて、六波羅へひかれて参りましたようで」
「六波羅勢の中に、兼綱はいたか、見えなんだか」
「出羽判官と駒を並べ、ひとつ軍勢の中にお見えなされました由」
そう聞くと、頼政は、
「・・・・ふ、ふ、ふ。・・・・いや兼綱も、やりおるの、やりおるの。ならば、まずよし」
と、暗闇の中で、ひとり、顎あご
の翁髯おきなひげ を吹き動かして笑ったようであった。
「唱よ、それ聞いて、いささか安堵あんど
いたしたわえ。眼の前の兼綱をすら、見破られぬとあれば、よも頼政を、宮方の同心とは、覚さと
りもしておるまい」
六波羅の眼が、こなたへとは、気振りにも、まだうかがわれませぬ」
大儀であった。眠る間もあるまいが、少しなと眠っておけ。わしも一睡しよう。──
あすはあすの風を見てのこと」
「では、御寝ぎょし
なされませ」
「怠りはあるまいが、朝夕、門辺かどべ
の掃除、常のようにな」
「下部しもべ
どもは、何も存じませぬ。お気づかいなく」
こうして、この家には、翌十六日、十七日、十八日と、それからの毎日にも、なんらの変化は見られなかった。老三位の起き臥ふ
しにも、表面、日ごろと違うところはない。
が、一歩、都心へ出ると、おびただしい鎧武者よろいむしゃ
の影に、人は眼を見張らずにはおられまい。
辻々に吹き寄せられている市人の群れは、しきりな武者の往来や、牛車、早馬などを、横目に見ながら、
「どしても、また一と戦いくさ
か」
と、暴風模様あれもよう
を気づかうように、ため息まじりのささやきで埋まっていた以仁王の脱走、源氏への令旨など、彼らはもう知っている。 |