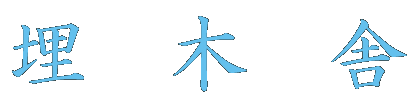ものの匂いも御座近くとわかる塗籠
の一間には、かすかな揺れもない切燈台の灯が、白々と立っていた。
宮のお眸を、ちらと、仰ぎ受けて、頼政は、御前にひれ伏した。
あとの二人も、やや退さ
がって、頼政にならった。
「令旨りょうじ
を」
以仁王は、すぐ、几案きあん
の上の折り奉書を取って、侍者の宗信へ渡され、宗信から三名へ下げ渡された。
ほかには、何も仰っしゃらない。
ほんのり充血したお顔である。すべては、それが語っていた。
「は。・・・・」
と、頼政も、令旨を拝受したまま、しびれたような感動につきぬかれていた。
「頼政。念のため、一読してくれよ」
宮の言葉だった。仰せを待つまでもなく、頼政も行家も、内見のみゆりしを乞うつもりであった。
さきに、草稿の案文については、もとより御相談にあずかっている。侍者宗信や少納言惟長にも、諮問しもん
されたことであろう。が大体、宮御自身、文章には達しておられるので、推敲すいこう
また推敲のうえ、浄書されたものと思われる。
「・・・・・・」
頼政が、披ひら
く。
行家と仲綱とは、そのわきから、手をつかえ、拝読する。
惟長は、そっと、明りを近づけた。
全文、漢字である。 |
| “東海、東山、北陸三道ノ諸国源氏、?ナラビ
ニ、群兵等ノ所ニ下ス” |
|
| と書き出され、 |
| “清盛法師、?ナラビ
ニ、従類叛逆ノ輩ヲ早々追討シテ応コタ
フベキ事” |
|
以下、四百幾文字の令旨は、実に烈しいお言葉で、書かれてあった。
清盛をさして、国家を亡ぼし、百官万民を悩乱のうらん
する毒賊であるといい、皇院を監禁し、国財を盗み、公領を私わたくし
に奪い、また仏法破滅の仏敵であるともいい、あらゆる罪悪を鳴らしている。これを見て、憤激しない者はいないような辞句である。
(激越な・・・・余りに激越な)
読み下しつつ、頼政にすら思えた。お若いのだ。つまり文章に出るお若さなのであろう。
地方武者を蹶起けっき
させるには、あるいは、この若さこそ、貴重かもしれない。自分が年を老と
りすぎているため、眼に強く感じすぎるという点もある。頼政は反省し、そこはむしろ、宮の壮志を見直した。
けれど、末尾の文へ来て、かれは、まったく眼をとめてしまった。
|
| ── “兼テ、三道諸国ノ勇士ニオイテ、追討ニ与力スル者ハ他日コレヲ賞セム。モシ、同心セザル者ニオイテハ、コレヲ、清盛従類ノ徒ト見ナシ、後ニ、死罪、追禁ノ罪科ニ行ハム” |
|
と、いうあてりは、まだよいとしても、結びに、
「── 即位の後は、功にしたかって、勧賞けんじょう
を賜うであろう」 としてある箇所だった。頼政は、その一行が、胸につかえた。
(── これでは、王もまた、私わたくし
に、帝位を望むものではないか)
と、宮のために、惜しまれるのであった。
また、義兵でなければならない挙兵の令旨が、いたずらに、勧賞けんじょう
を餌え とし、野望の徒を糾合きゅうごう
するような響きにも聞こえはしまいか。
頼政が、生涯、忍にん
を守って、今日を待っていた志とは、大いに違うものがある。頼政は、ふと、苦悶くもん
を覚えた。またしても、まよわずにいられないものにぶつかっていた。
「頼政、見終わったら、十郎行家にそれをさずけ、ただちに、行家を発足させたがいい」
宮は、頼政がそれを、余りにいつまでも、凝視ぎょうし
しているので、彼の老いがさせる業わざ
かと、わざと、こう急きたてられた。
もっとも、今しがた、どこか遠くで鶏鳴が聞こえたようである。
みじか夜だ、夜明けは近いのであろう。
「おう、明けぬまに」
頼政も、つい、お答えしてしまった。
運命にはあやつられない。自分の運命は自分で作って行く、として来た頼政も、このとき、何か、足もとへ来た大きな波にさらわれたような、自主のない自分が感じられた。 |