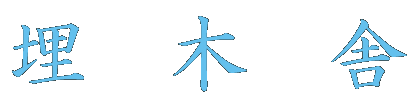「はて、まだか、まだ生まれぬのか」
清盛は、さっきから何度、同じ言葉をもらしたことかわからない。
彼は、老妻の二位ノ局
(時子) とともに、御産所へ近い一殿
に夜半過ぎからすわっていた。いや起た
ったりすわったりであった。
「二位」
「はい」
「まいちど、そっと参って、御几帳みきちょう
の内を、うかごうて来い」
「でも、たった今、戻ったばかりでございますのに」
「が・・・・。あの、苦しげな呻うめ
きは」
「初産ういざん
でもございますし」
「そもじが、重盛を生んだときは、このようではなかった」
「人にもよりまする」
「あれ。・・・・また、あのように」
「あなたのように、そうそわそわ遊ばしても、なんの効か
いにもなりませぬ」
「あわれ、清盛も、兵事や政変などならば、こうも乱れはしまいものを」
「院には、かなたの一間で、おんみずから御加持ごかじ
を上げていらっしゃいます。あなたとて、御法体ごほったい
のてまえもありましょうに」
「おれに、護摩を焚け、経を読めと言っても、それは無理だ。まや、功力くりき
のあるはずもない」
「女人が産む苦患くげん
とは、そのむすめの父祖の罪障が、さまざまな魔となって、安産を妨げるためとか聞いておりまする」
「おれのせいだというのか」
「── と申すのではありませぬが、武門の過去には」
「た、たわけたことを」
清盛は首を振った。背筋にはうものでも振り落とすような格好をして、二位ノ尼を、どなりつけた。が、修法の声や振鈴しんれい
の音ね に、それは、次へも聞こえなかった。
祈祷の壇は、一ヶ所や二ヶ所ではない。清盛夫妻のいた南側の一棟ひとむね
から広床へかけても、一団の修験者しゅげんじゃ
が、ひしめきすわって、数珠じゅず
をおし揉みおし揉み ── 魔魅まみ
調伏ちょうふく を行ぎょう
じていた。
りんりんと、振り鳴らす鈴、わんわんと読み上げ読み上げ、声をからす千僧の読経、そして、護摩の炎、もうもうと屋をつつむ煙。── その中に、産婦は、うめいていたのである。
「ああ、疲れた。・・・・おれすら、疲れ果てたのに」
清盛は、ふと、心のうちで、徳子と呼んだ。娘の幼顔おさながお
を思い出し、何か、自分たちが、むらがり寄って、罪もない彼女を酷ひど
い目にあわせているような気がしないでもない。
そのくせ、心の一隅いちぐう
では、
(男の子であってくれよ。生まるる子は、皇子であるように)
という願いが、どうしようもないほど、彼の胸を占めていた。
もし、皇子であれば、自分たち夫婦は帝室の外祖父、外祖母である。これ以上の階はないのだ。平家全体の家格と安泰を一層固め、ひいては、院の超勢力に対し、もうひとつ階を登った地位でものをいえようと、ひそかに思う。
なんといっても、法皇には人臣にない絶対権がある。ときには、朝廷以上といってよい御存在であり院政という厄介な機関もある。清盛はその超権力の前に、何度、苦杯をなめ、さいごの屈服を強いられているかわからない。
もし自分が、かつての藤原氏なみに、皇室の外祖父ともなれば
── と、これは常にうかがっていた願望でもあった。だから彼は、子の親としてのよろこびと、別な欲望との、ふたつを、御産所の生う
ぶ声へかけていた。── 可憐かれん
な御几帳みきちょう の内の苦しみを耳にするたび、彼が、顔じゅうに、胸騒ぎをあらわして、うろうろしたのも、無理はない。 |