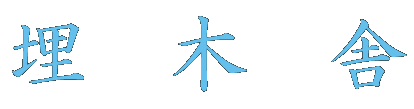上甲板で出迎えたのは、参謀長のクロッス中佐であった。彼はまだ三十代であったし、それにもともと威勢の悪くない人物なのだが真之の目には雨に打たれたむく
犬のような印象にうつった。ひとつには口ひげが伸びすぎ、潮風やら爆煙やらがこっぴりついてすだれのように垂れてしまっていたせいだったかも知れない。
真之と山本大尉は、司令室に通された。他にたれもいなかった。どこからか叫喚
の声がひびいて来る。やはり尋常な空気ではなかった。
(つまらない目に遭
うものだ)
と、真之は敵に対してではなく、自分に対して思った。降敵の城に軍使として乗り込むということは絵物語ならいかにも爽快な光景なのだが、いざその役目を自分に割り当てられてみると、陰惨さの方が先立った、おそらくネボガトフが出て来るであろう。それに対してどういう態度をとっていいのか、真之は戸惑う思いがした。待つ間も通路をしきりに叫び声が走っている。
山本の顔が、緊張でこわばっていた。
「いざとなれば武士らしくいさぎよく死のう」 と山本はくりかえし自分に言いきかせては落着こうとしていたが、真之はべつにそう思わなかった。彼には通路の叫び声の正体が分かっているのである。真之はここまで案内されて来るまでの間に、将校や兵たちが何をしているかを一瞥
して見当をつけてしまっていた。彼らは信号書や機密書類などを海中に投棄するために号令を発したり、注意事項を叫んだりしているだけのことだと見ていた。そういう書類の始末というのは彼らがはっきり戦闘を放棄し降伏しようとしている証拠で、むしろあの騒ぎ
は真之らが軍使として安全な状態にあることを傍証づけているようなものなのである。
やがてネボガトフ少将が入って来た。
真之らは、立ちあがった。相手のネボガトフが敵将であるとはいえ、海軍礼法によって階級相応の敬礼をしなければならない。真之はその後も同少将のことを書くときに敬語を用いているが、それが海軍礼法の強制によるものというより、彼が属した時代のごく尋常な礼儀感覚であるというほうが正確かもしれない。
ネボガトフは真之の懸念を裏切って一向に降将らしくなかった。この白髪白髯
の肥った五十男は笑顔と大ぶりな所作で入って来て、いきなり自分の体をたたいた。
「こんな服装で申しわけありません」
と、フランス語で言って握手をもとめた。真之は握手しつつ、なるほどきたない服装だと思った。
「少将、汚穢
ナル戦衣ノ儘 ニテ出来
リ、鄭重 ニ握手セラル」
というのは、真之の文章である。大尉山本信次郎の後日談では、
「汚れはてた石炭積みの作業服を着ていた。そのときはじめて知ったのだが、ロシアでは戦争をする時は作業服を着るものらしい。わg海軍は死装束のつもりで、晴れの軍服を着る」
と、ある。が、ネボガトフその人の人柄については、
「非常に善良そうな人」 という印象を真之も山本も受けた。 |