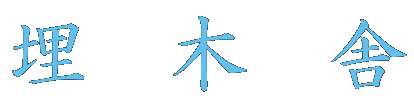参謀旅行というのがある。
これも、フランス陸軍にはない。欧米の他の国にもなく、ドイツだけのものであった。創案者は、モルトケらしい。
統裁官はつねに戦術の大家がこれにあたる。参謀学生を引き連れ、実際の山野を舞台に、
「もしあの山ぎわの間道から敵の騎兵一個大隊が出現したらどうするか」
とか、
「この状況下で砲兵は野砲三個中隊しかない。それをどこへ置けばいいか」
といったふうなことを統裁官がつぎつぎに質問し、相手の返答が悪ければ罵倒し、修正し、さらに戦いをすすめてゆく。戦術は状況と地形によって流動するものだが、それを実際訓練するにはこの参謀旅行ほどいい方法はない。
その第一回の参謀旅行は、明治十八年十一月、茨城県下で行われた。
戦場は、関東平野である。その第一日は利根川のほとりの取手
町から開始された。
好古も、参加した。この時の話を、メッケルの研究家宿利しゅくり
重一氏が、晩年の陸軍中将藤井茂太に聞いている。藤井は好古と同期で、この当時砲兵中尉であり、日露戦争では第一軍参謀長をつとめた。
── なにもおれたちは知らなかったな。
といった調子で、正直に語っている。藤井中尉はメッケルから、
──
おまえは兵站監へいたんかん になれ。
といわれた。
兵站というのは、作戦のために必要なあらゆつ物資
── 弾薬、食糧、衣服、馬匹ばひつ
などを筆頭に ── を後方にあって確保し、それを作戦の必要に応じて前線へ送る機関で、近代戦をやるうえでこれほど重要な機関はない。
が、日本人の戦争の歴史は、一、二の例外を除いてはすべて国内が戦場になっており、兵站というほどのものが必要であったことがない。強いて例外を求めれば、豊臣秀吉の朝鮮出兵のとき、石田三成が近代軍隊の用語でいう兵站監に任じ、そのための船舶を往来させつつ戦場への兵糧送りをした例があるにすぎない。
「兵站とは何だ」
と、藤井は学生たちに聞いてまわったが、たれも知らない。のち日露戦争における第二師団参謀長になった石橋健蔵という歩兵中尉が、
「つまり食糧だから、梅干を少々集めておけばいいだろう」
と解釈し、藤井はそのようにした。メッケルはあとで咆ほ
えるように怒った。しかしこの当時の日本人の卑小な生活感覚からすれば、ヨーロッパで発達した近代戦の規模や質というものが、知識としてはなんとか理解できても、感覚としてはどうにも想像できなかった。
「鉄舟をもって渡河する」
と、統裁官のメッケルが言うと、鉄の舟が浮かぶはずがない、と大まじめにこのヨーロッパ人に食ってかかった学生もある。 |