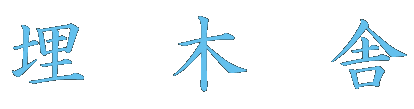ここに、三位中将
の旧臣で、木工允
友時 という侍があった。
その友時は、昨日、重衡の中将が、市中を引きまわされつつ、群集の一部から、石つぶてや泥草鞋
を投げつけられ、小八葉
の車も打ち破らるるばかりな目に遭っていたのを見──
「あな無残、これがつい三、四年前までは、西八条の出入りに、先駆
けの騎馬や、車添 の百臣に囲まれて、時めき給う公達のおすがたか」
と、面をおおうて、逃げるが如く、家へ帰った。
そして、一晩中、泣き明しでもしたのだろうか。次の日、彼は腫
れぽったい顔をもって、重衡の中将が監禁されている堀川ノ御堂の辺を、うろついていた。
ところへ、ちょうど、土肥実平と供の一群が、義経の許から帰って来た。それを見ると友時は、いきなり物蔭から走り出して、
「お願いの者でござりまする。あわれ、お慈悲をもって、お聞き届け給わりませ」
と、必死な顔つきで、その人の馬前に立ち、そして下へ、ぬかずいてしまった。
土肥の郎党たちが、
「なにやつだ。そこ退
け」
と立ち騒ぐのを制して、実平は、何か仔細
があろうと、友時のことばを、自身、訊いてみた。
友時は、こう訴えた。
「てまえは、木工寮
の小役人ですが、以前は、三位
中将殿に仕えておりました者。それも召次
の小侍でしたから、軍 のお供は一度も致しておりません。──
とは申せ今日、旧主のお傷
ましい有様を見、いても立ってもいられない心地です。せめて、お慰めの一言でも申し上げたいものと、じつは今朝から御幽居をうかごうておりましたものの、警固のきびしさに、ただ、うろうろしていた次第です。どうか、おゆりしくださいませ。よそながら、たとえ寸時のお目通りでも」
嘘いつわりの言えそうな人物ではない。
実平は、許した。彼の腰の刀だけを取り上げさせて、警固の垣の内へ入れてやった。
草茫々
と荒れ果てた庭を巡って、友時は、御堂の下へ、そっと寄った。
すると、破れの簾の内から、
「友時ではないか」
と、聞き覚えのある人の声がした。
友時は、われを忘れて、階
を駆 け上がり、縁の端にひれ伏して、
「変わり果てたおん姿、もう、何からお話申し上げたら、よろしいやら・・・・」
と、ただ眼をぬぐうばかりだった。
重衡も、夢かと、怪しむような眼をみはって。
「やよ友時。どうして、これへは来つる?」
「御警固の実平殿に取りすがって」
「では、やはり土肥殿の情けであったか。さても、そちの姿を見れば、すぐ問いたいが」
「かの君 さまの御消息でございましょうがの」
「それよ・・・・右衛門佐
ノ局 には、今でも変りのう内裏
においやるであろうか」
「しかと、さように、承っておりまする」
「あれほど深う契
った男が・・・・と、この重衡を、お心の底で、どのように怨
んでおらるることかと、夜々、思わぬ夜はない」
「以前はよく、お文使いなども仰せつかり、下臈
のわたくしなど、嫉 ましい思いをいたしたものでございましたが、その後、世がこうなっては、まこと、是非もございませぬ。なんで、かの君
さまとて、殿をお怨み申し上げましょうか」
「一門の内には、妻子や恋人まで携
えおうて、西国へ下った者も少なくないのに、重衡はつい、かの君
にいいおくこともせず、その後の便りすらも送っておらぬ」
「それとて、お心にないのではなく、一門の御浮沈に当って、重きにおわす殿のお立場は、かの君
さまにも、ようお分かりでございましょう。さっそく、御文
をしたため遊ばしませ、友時が、お使いをいたしましょうほどに」
「なに。そちが、文使いすると申すか」
「内裏の深くにおわす君、めったに、近づき参らすわけにはゆきませぬが、黄昏
れ時、ひそかに、お局の下口
へ忍び寄って」
重衡はさそっく筆をとった。一別以来の想いを細々
と書きつづって、
「きっと、かの君
のお返しを、待っているぞ」
と、友時に託した。
警固の武士は、その場を、隙見していたらしく、友時が退
がって来ると 「お預かりした書状を見せよ」 と責め、それを取り上げて、実平の前へ持って来た。
── が、纏綿
たる恋文だったので、実平は笑って返した。
その夕、友時は、内裏の奥へ忍んで、局の下口
の辺に潜み、右衛 門佐
が見えるのを気長に待って、重衡の文をそっと手渡した。
そして 「おん返しを ── 」 と、小坪
の木蔭に隠れてまた、待っていたが、小蔀
からもれる灯影の内には、さめざめと忍び泣く声の気配がするだけだった。
が、そのうちに、ようやく、局は返書をしたため終わって、
「このふた年
ばかりの、明け暮れの苦しさは、筆には尽くしきれぬ。ただ察して給
べ」
と、死ぬばかりな思慕を、ことばのうえにも、くれぐれ託して、再び、局の内へもどり入るなり袖
を被 いて泣き伏した。
彼女の返し文も、もちろん、土肥実平の検問の眼にふれた。匂
わしい涙のあとや仮名書
きの乱れは、男の心をかきむしらずにおかないほど美しい。
しかし坂東武者は、男同士の武功には、妬
みを感じても、こういう恋をうらやましいとはしなかった。むしろ愍笑
に似た気持で、看過していたばかりでなく、その日、重衡の中将から、願い出たことも、また即座に許した。
やがて、夜も更
けてから、一輛 の女房車が、御堂の荒れ庭へ、車のまま入って来た。
まろび出るがごとく車を降りた人は、右衛門佐ノ局であった。
深く灯の色をさえ隠した壁代
の裡 は、何か妖
しいまで、ひそやかであった。そしてただ涙に濡
れ合うらしい男女 の短い半夜を、さすが警固の武士も、邪
げはしなかった。いや特に実平からも 「── 遠くにおれ」 と、厳命されていたもののようである。
あたりの白む前に、車は、なお尽きぬ名残の人を乗せて、暁
の黒い霞 のかなたへ消えて行った。
彼女は、亡
き桜町中納言のむすめとか、奈良の民部親範の女
とか伝えられている。それすらさだかでないほど、身寄りも少ない淋しい女性であったらしい。もちろん、重衡の中将とは初恋であり、この世で知ったただ一人の男性だった。しかもその人とは、都と西海の遠くに隔てられ、土肥実平の情けによるわずか半夜の再会が、ついに、最後の契りとなってしまった。なぜならば、やがて後日、重衡の中将が、奈良の衆徒の手で斬られたと聞こえたので、彼女も内裏を出て、髪をおろし、その生涯を、山家に隠してしまったからである。 |