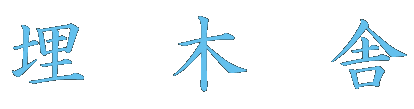陽
は高くなり、戦いは、すでに終熄
を告げていた ──
二月七日、巳
の下刻 (午前十一時)
ごろ、義経は、輪田ノ岬に陣して、
「搦手
の本軍は、ここにあるぞと、諸手
の兵へ、眼にも見ゆるように告げ知らせよ」
と、言い渡した。
岬の渚
から、松原へかけて、幾十旒
もの白旗が立ち、昨日まで、この地の山海を彩
っていた平家の旗に代った。
また、おなじ時刻のころ。
大手軍の蒲冠者
範頼 は、生田ノ森から、西国街道の山手を一掃して、もと太政入道の山荘、雪ノ御所の跡に、陣所をおき、梶原以下の軍勢も、附近の夢野あたりに、それぞれ、兵馬をまとめて、今しがた、三度の勝鬨
をあげて祝したということも、聞こえていた。
義経は、さっそく、使者を選んで、
「ともに、力を協
せて、鎌倉どのの御使命を辱
めず、一挙 、今朝の勝ちを得たること、同慶のいたりです。陣務、始末の後、親しく拝面をとげ、何かのおん物がたり、仕
らん」
と、祝詞を申し送った。
使いには、佐藤継信、忠信の兄弟が行った。
二人は、やがて、帰って来て、
「蒲殿
には御書面を手に、いと、御満足なていでした。あの殿も、今日ばかりは、凛々
しゅう見上げられ、辺りの侍大将も、はや、生田の神酒倉
の酒瓶 をひらき、祝いさざめいておられまする」
と、模様を話した。
「そうか」
と、聞き終わった様子で、義経が、床几
を立ちかけると、継信は、言いにくそうな口吻
をすぐつづけた。
「なおまた、梶原殿からも、御伝言がございましたが」
「平三
景時 どのから?」
「はい」
「なんと」
「──
九郎の殿には、何もかも措 いて、ましぐらに、平家の船がかりせる浜辺に駆け出で、さだめし、よいお手柄を獲
られたことであろう。院がお待ちかねの三種の神器も、つつがなく、お手に収められたか否か、吉左右
、早く承りたいもの・・・・と、かように、満座の中で仰せられました」
義経は、黙って聞いていた。わずかなうなずきと微笑のもとに 「そうか」 と、それにも同じ短い一語をもらしただけで床几
を離れた。
陣所は、もと来迎寺
の跡である。
朽ち傾いた山門、欠けた塔、瓦礫
、かつての、入道清盛が全盛時を偲
ぶよすがもない。あるのは、自然の風化力だけである。
義経は、渚
へ出た。平家の大小の兵船も、その一艘さえ今は見えない。── 淡路、屋島、そのほかの島々さして、木の葉のように逃げ落ちて行った。
「・・・・むりはない、梶原も嘲
おう。義経には、なんらの功もなかったわけよ」
彼は、自分のとった作戦と進路を、過
ったとは思っていない。が、誇る気にはなおなれない。
鵯越えから、直接、坂落としに、敵の中核へとこころざした彼の突破軍も、途中、能登守教経や、幾多の平軍の将に、必死な抵抗を受け、ある時間を、血路に費やしてしまったのは、どうにも、是非のないことだった。
──
が、そにため、三種の神器と、主上を乗せた御座船は、逸早
く、浜を離れ、ここへ一ときの差で、殺到した義経は、ただその船影を、沖の遠くに見ただけであった。
「口惜しさよ」
と、いまも思う。
けれど、それは、ただ功名を逸したことを悔いるのではない。
単なる軍功の競いなら、そして、討ち取った首の数を誇るだけのことなら、義経の立場は、網の魚をつかみ捕りするほどな意のままにも出来たであろう。
あの時、浜にはまだ、平家の兵船が、いくらも、まごついていたのである。
「助けよ」 と、泳ぎつこうとしておぼるる兵、 「戻せ戻せ」 と陸から叫ぶ逃げおくれの将士など、憐
れむべき敗者の悲泣図
が、浜一帯に見られ、義経も、目撃していたのである。
が、義経は 「逃ぐるを狩るな。逃ぐる船へ、むだ矢を射るな」 と、そうした敵へは、わざと、眼を逸
らしたのだった。
そして、ひそかに、思ったのは、
「もし、われに、水軍だにあれば」
ということだった。
水軍を持たない源氏。これは、ぜひもない。
それを、前提としての、こんどの作戦でもあったのだ。義経の悔いは悔いとして残ったものの、
「ともあれ、自分のすべきことは、全力を尽くしていた」 という信念になんの動揺もなかった。梶原はおろか、何者にも、その点では、いささかの恥も卑下
も抱くものではない。 |