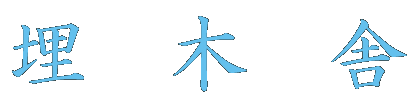飲んでも、赤くはならないし、めったに、酔いも見せない知盛だった。重衡は、日ごろ飲めない方だし、さっきの時忠の言葉にも釘
を打たれたかたちでいたが、知盛は、面つら
当てのように、しきりに飲んだ。そして、意気軒昂けんこう
たる風を見せた。
時忠は、この甥甥おい
を、じつは愛している。行く末、よい男になろうと見込んでいるのだ。けれど、こいう言動には、年長者がよく若者に抱く、生意気なという小面憎こづらにく
さを覚えずにいられない。
「左衛門督。相国の御命は、しかと、つたえ申したぞ」
「承うけたまわ
った」
「なお、もう一条、糺ただ
しておけと、仰せつかったが」
「まだなんぞ」
「されば、今日の首帳くびちょう
には、宮の御首級みしるし も、頼政の首級も、書かれておらぬが、大事なさそうに二人にの首級が分からぬではすまされぬぞと」
「ははあ。それで父禅門には、今日の合戦に、よくしたとも、大儀であったとも、おねりらいがないのであったか」
知盛は、父への甘えを持っているのだ。褒ほ
められないのが、不平だったのである。── と分かって、時忠も苦笑をもらした。
「仏作って魂入れず、ということもあれば、御懸念はむりもない。しきりなる取沙汰では、宮には、頼政とともに、奈良へ入られたとか、吉野十津川の奥まで落ちて行かれたに違いないとか、はや、臆測おもわく
がいわれておる」
「ばかな」
知盛は青白い酔いを、眉にぴりと見せて、
「一つ一つ敵屍を数えても、七十名は出ぬわずかな数、討ちもらしておるはずはない。・・・・そのため、後には、忠度ただのり
殿が残っておる。やがて忠盛殿が探し当てて、西八条へ罷るであろう。たれが、そのようなたわけたことを言い出すのか」
と、吐き出すように言った。
そして、不快の吐きついでに、
「このさい、池殿には、どうしておられるのか」
と、反撥的に訊き出した。
つねに、池頼盛を疑いの眼で見ている同族間では、この数日、たれもが、知盛と同じ疑問を抱いていたに違いない。
時忠は、うなずいた。知盛の不安を、彼もまた、不安としていたからである。
「いや、その池殿の兵馬は、今夕、相国の直命を受けて、八条女院へ向かわれた」
「なに、池殿が兵を率いて、八条女院へ向かわれたと仰っしゃるのか。あはははは・・・・これは奇態なことになろうぞ。盗人の巣へ、盗人を討手に差し向けたようなもの。ワハハハハ、聞いたか、重衡」
重衡は、答えなかった。
つと起た
ち上がって、あたりの部将をうながし、
「兄君。はや、御出馬を」
と、駒こま
を呼んだ。
「おう、立とうか」
体中から金属的な響きをゆり起こし、彼も、ゆらと腰を上げて、馬の上になった。したたかに酔っているのだ。しかも、酔えば醉ほど青白い凄味すごみ
が面に充ちてくる。 |