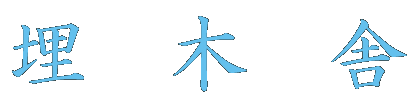残ったのは、六十余名、それがすべてである。その先も、宮に供奉
して行った正味の人数であった。
帰すべき人は帰し、別るべき者とは別れ去って、頼政は、
「これで、よし」
と、心の荷もいくらか軽くなったような眉まゆ
に見える。
人馬の列は、まだ黙々と、山の尾根を進み始めた。しばらくは、羊腸ようちょう
たる道がつづく。
陽ひ
が高くなるにつれ、谷々の白雲は霽は
れ、視界は遠くにまで展ひら けてきた。右の谷間をへだててかなたに見える一峰と諸伽藍がらん
の屋根は、上醍醐かみだいご にちがいない。
左方を望めば、喜撰獄、立花ノ峰。また、足もとの沢を、南へ落ちて行く水音は、やがて宇治川と一つになる志津川の渓流であろう。
「オオ、かなたに宇治川が見え出した」
「宇治橋のたもと」
「川のかなたの楊柳かわやなぎ
や、平等院びょうどういん の甍いらか
も、かすかに」
いわず語らず、皆、宇治を一目標としていたのである。 「事なく、宇治まで行き着けば、奈良は半日ともかからぬ行程」 としていた思いが、声になって、口々から出たものだった。
しかし、頼政は安んじない。彼は眸を西北へ移していた。そして、俗に京道という
── 伏見から木幡山こばたやま
の低い背を越え、宇治川に沿って来る一すじの道のはるかに、その眼をとめた。
「・・・・ああ、はやくも平家の手勢が」
頼政の眉は曇った。── 木幡の峠あたり、すでに、平家の旗と、兵馬の影が、点々と見える。
敵の物見か、でなければ、京道と山科街道を扼やく
して、われを待つ兵か。
いずれにせよ、もう敵と接しているのだ。猶予は出来ない。頼政は、馬上に伸びあがり、鞭むち
をかなたに指して、
「やよ人びと。六波羅勢は、はや木幡を越えつるぞ」
と、全軍の上へ叫んだ。
「── 敵が櫃川ひつがわ
を渡り、大和街道を駈か ければ、宇治橋までは、ただひと息。もし彼に先せん
を取られ、宇治橋の詰つめ (たもと)
を塞ふさ がれては、奈良へも通れぬ、後へも退けぬ。急げや、おのおの」
おうつと、六十余名が、ひとり残らず、体から声をふるい出した。
急ぎに急いで、ふもとへ、なだれ降くだ
る。
山下の里は、岡星郷。
今日に限って、真夏のような暑さとなった。兜かぶと
の下は蒸れ、鎧よろい の金具は焼けて、どの武者顔も、まるで焔ほのお
だった。ことに、馬の疲労ははなはだしい。
「余す道は、もうわずかぞ。宇治橋までは、あと半里よ」
頼政は声をからし、のべつ励まし励まして行った。 |