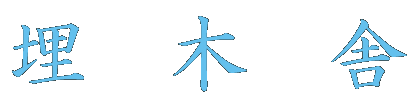まだ三十歳の若宮である。以仁王
が、世事にも、政情にもうといお方だったのはぜひもない。
いわば純情、いわば世間知らず。
いちど僧門には入って、また還俗げんぞく
したというほか、廟堂びょうどう
に立った御体験もなければ、人交ひとまじ
わりもなく ── さりとて生活の御艱苦ごかんく
もなめてはいず ── ただ三条高倉の御所に領田 (扶持) を添えて置かれて来ただけの “忘られ人” に過ぎなかった。
詩を作り、絵をよくし、また、玉笛を弄もてあそ
ぶ、といったような貴公子的の閑戯には、人より優れておられたらしい。
しかし、このお人が、 「平家をたおさん」 などという発起をどうして抱いたものか。
おそらく、宮自身でも、そんな首謀者に立とうとは、頼政に説かれるまで、思いもしていなかったことであろう。ことに、相そう
ノ少納言しょうなごん 惟長これなが
などから 「── 宮には自然、帝王の相そう
がお貌かお にそなわっております」
などと言われなかったら、御不平も、欲望も、なお眠ったままお胸におかれていたにちがいない。
身は後白河の子、前さき
の天皇は、わが異母弟おとと ではないか。さるを、母が清華せいが
の出でないばかりに、親王にも立たず、埋もれ木にされてきた。平家を呪のろ
う洛中の不穏も、頼政のすすめも、われに藪門そうもん
を出よと、春を告ぐる声であろう。相そう
ノ少納言の予言は、それの天示にちがいない」
幻想が不平を育て、不平が幻想を培つちか
う。
わけて頼政から、 「宮に平家討滅のお志あるは、法皇におかれても、御満足なのです。事をともに挙げるはむずかしいが、宮の起つ時あらば、院も後巻うしろまき
して、軍いくさ を援けんとも、仰せられました」
── と聞かされたからは、一そう、決意を固められたものだった。
要するに、宮は仮体であって、主体ではない。主体は、老三位頼政といえる。
いや、これも平家をして、八方の禍に困憊こんぱい
させようと計っておられた後白河の一策であり教唆きょうさ
であったと、見られないこともない。
しかも、宮は宮のお立場から、あれこれ、必勝の工夫くふう
をこらされた。── 生涯の大事と、以来は、風雅も捨てて、ただ秘策を按あん
じておられた。
お胸に恃たの
む第一のものは、もちろん 「院」 の力である。うしろだてには、父法皇や近臣の実力がある、自分が起って、戦乱状態になれば、機を計って、 「院」 も表面に出るという頼政を介しての黙契を、かたく信じて疑おうともなさらない。
ところが、事態は、一変した。
恃む
「院」 はなくなった。
院の諸公卿は、追放され、法皇は、幽所に拘禁されてしまった。
あの騒動には、宮も、
「もしや、ここへも、平家の手が」
と、外の世音に、一時は、恟々きょうきょう
としておいでだった。 |