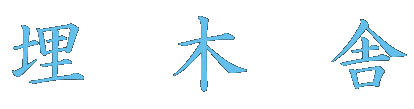「なぜ、主君を見て、逃げたか」
という調べに対して、松王の答えた言葉から、その夜、意外な事実が、清盛の耳にはいった。
松王は、数日前に、都賀
の里の、母のもとへ、帰っていた。
その日、雪ノ御所へ帰るために、生田いくた
ノ森まで歩いて来た。すると、行きがけにはなかった関所の柵さく
が出来ているので、怪しみながら通りかけると、森の蔭から、数名の武者が現れて、彼を捕らえ、
「この道を通ったのは、おまえが仏陀ぶつだ
から選ばれて、人柱ひとばしら
になれと、前世から約束されているのだ。後世ごせ
は、よい月日の下に生まれるぞよ。── 観念して、あれに籠こも
れ」
と、半なか ば腕力で、半ば諭しながら、一宇いちう
の御堂のうちに、放り込んでしまった。
そこには、松王のほかに、まだたくさんな同じ年ごろの童わっぱ
が、うようよいて、
「帰して給べ。帰して給べ」
と、泣きわめいていた。
番の武者は、格子の外から、
「泣いたとて、帰しはせぬ。なむあみだぶつと、念仏をとなえろ。後世ごせ
を願って、ただ念仏を申しておれ」
と、ときどき、菓子などを入れてくれた。
けれど、どんな食べ物も、見向きする子はいない。童わらべ
たちは皆、やがて、石船に乗せられて、築港の石とともに、人柱ひとばしら
として、沈められるのだということを、いい聞かされていたからである。
松王も一たんは仰天したが、ひとつの嘘うそ
を思いついた。嘘には違いないが、それは先月にはほんとのことでもあったので、非常にうまく言えたし、また、事実、雪ノ御所の侍童には違いないので、言うことに間違いはなかった。
「やいやい。わしを捕まえて、人柱に立てるなら、その前に、寺戸の山荘へ行って、五条那綱くにつな
様と、朱鼻あけはな の伴卜ばんぼく
様に、よく念を押して来いよ。わしは、入道相国の侍童、松王という者だぞ。そして今日は、雪ノ御所の御用で、寺戸の伴卜様の許へ、お使いに行った帰り途みち
だぞ、ヘタなまねをして、自分たちがアベコベに人柱になるなよ」
武者たちは、驚いた。
そして、 「このことは、決して口外するな」 という約束の下に、彼のみ、放されて帰って来たというのである。
「・・・・相国のお姿を見て、なぜ逃げたのか、わたくしにも、分かりません。このことをお訴えしようと、必死に思い込んでいたのに、相国がお歩きになって来るのを仰いだら、急に、怖おそ
ろしくなって、思わず庭へ跳び降りてしまいました」
松王は、そう告げてしまうと、もうふるえてもいなかった
徹宵てっしょう
の詮議せんぎ が始まった。阿波民部、日向太郎が、第一に召し呼ばれた。
二人は、何も知っていない。
技官の野見隼人、橘唐雄からお
、久能大造、飛騨多門など、続々、吟味所に呼ばれて糺ただ
されたが、彼らもまた、
「人柱を立てるなどとは、ゆめ、考えたこともありません」
と、みな言い張る。
そのうちに、分かった。船夫ふなこ
千人を預かっている並河なみかわ
権六ごんろく という六波羅一門の武者頭むしゃがしら
である。
先ごろ、法皇が法華道場の常住として残して行かれた東大寺の僧侶そうりょ
が、権六に向かって、
「入道相国は、余りに、罪業が多いお人である。いかほど、築堤を企てようとも、到底、成就はおぼつかない。けれど、ここに三十人の清童せいどう
を人柱に立て、わしが二十一日の祈願をこめるならば、かならず海龍王かいりゅうおう
の怒りをなだめて、築堤の礎もと
を、ゆるぎなくして見せるであろう」
と、語ったという。
その東大寺僧に、深く帰依きえ
していた並河権六は、これを両奉行に諮はか
ろうと思ったが、何ぶんにも、この東大寺僧は、法皇をめぐる近臣たちの口吻こうふん
そのまま、清盛のことといえば、悪しざまに誹そし
るので、自分一個の念願の下に、二十一日の祈誓をその僧侶といい合わせ、生田ノ森で、人柱ひとばしら
の子ども狩りを、ひそかに部下にやらせていたものと分かった。 |