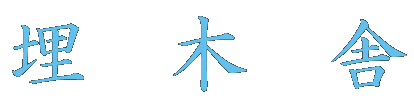奥の泉殿
には客が居た。内輪の客らしく、主の信西、妻の紀伊ノ局もいた。時節柄、ひそとだが、厨房ちゅうぼう
の料理人を、廊の間まで招いて、鯉こい
の生キ作りなど目の前でさせながら、酒を酌く
み交わしていたのである。
「ちっ・・・・。うるさいの」
客の興を憚はばか
って、信西がふと、舌打ちすると、
「見てまいりましょう」
と、息子の、長憲ながのり
というのが、立ちかけた。
信西は、息子の耳もとへ、そっと言った。
「文覚という、うるさい野僧だ。内裏へも、献言書などを投げ込んでおる。よい程にいいすかして、追い返せよ」
長憲は、のみこんで、車寄せへ出て行った。そして式台から、文覚を見下ろした。
「文覚とは、御僧か。父は、おるにはおるが、大事なお客人まろうど
とお話ししておられる。御僧の献言書とやらも、見られた由、それで、よろしかろうに」
「あなたは、何だ」
「当家の三男」
「失礼だが、あんたでは分からん。信西どのを、お出しなさい」
「出せとは、礼をわきまえぬお言葉よ」
「いや、礼は欠いていない。野僧はここを訪うに、三日を費やしている。ちょっと、奥からお顔を出されるぐらいが何の労ぞ。しかも、私事わたくしごと
ではなく、国事を憂うる文覚の言を聞くに、寸時を惜しまるる法たある」
「御僧のような訪客は、じつに、珍しくありません。おそらく父も、そうした憂国の談義は、聞き飽きていることでしょう」
「だまんなさい!
お息子。文覚は、かような権門へ、粋狂に足を運んでいるのではない。日々夜々、靫負庁ゆきえのちょう
の牢獄ろうごく より引き出されては、河原で打首になる人びとの数はもう幾十人ぞ」
「静かにしてください。お客人の耳ざわりだ」
「そうか。・・・・ならば、奥なる信西入道の座まで聞こえると見えるな。よろしい。ここから話す。客あらば、客も聞き給え」
文覚は、突っ立ちあがって腕をのばした。年々、那智なち
へこもり、あのすさまじい山風と滝しぶきの中で、喉のど
もやぶれよと、経文を読誦どくず
し、二十一日の荒行をやって来ることを、今も欠かさない彼である。意識して、すこし大声を出すとなれば、梁うつばり
も揺れ、幾重の壁も通して、館やかた
中の耳を奪ってしまうぐらい、何でもない。
「やよ。この家や
の主あるじ 。ちまたの沙汰さた
と、軽んじるな。天の言わしめることと思うて聞き給え。── 聞説きくならく
。信西入道が主となって、乱後、戦犯の人びとを斬き
ること、六道ろくどう 鬼界きかい
の地獄図に異ならずとか。── 甥おい
をもって、叔父おじ を斬らせ、兄をして弟を討たせ、子をもって父の首級をあげしめるなど、犬猫いぬねこ
の畜生仲間にも、あることか」 「・・・・・・・」
「── なお。聞く。朝議日々、信西入道が口を開くたびに、かならず幾人かの生命に死刑の宣出づと。義朝に強いて、父為義の首を朝ちょう
に出させ、なお弟どもを討たせても、よしとはせず、為義の老妻を追わせて、池に投じ、幼児おさなご
の幾人をも道にならべて、これを刺殺す。── その無情さ冷酷さ、たれか、憎まぬ者があろうか」
「・・・・・・・」
長憲も家人けにん
も、圧倒されたかたちである。まるで滝の音の前に立ったように、この間、一言も酬むく
うことが出来なかった。
「しかも、これらのことすべて、信西は、袞龍こんりょう
の袖にかくれ、勅宣をもって、武士に命ず、という。朝廷をして、鬼畜の怨府えんぷ
となすもの。臣として、これにまさる不忠やある。── 弘仁元年このかた、帝王二十六代、三百四十七年の間、国に死刑の宣なく、都に兵乱なく、民を視み
るは子のごとく、仁愛を御心として、世々の平和を祈らせ給うて来た皇室も、かたちは有れ、まことの御相おすがた
はなくなった。ああ残念っ」
文覚は、腕くびの数珠を外して、右手に握り、その拳こぶし
を打ち振って、言うのであった。数珠は風を切って鳴り、弁舌は、雲を呼ぶ慨がある。
自分の語気に自分を燃やし、激し出すと止まるのを知らないのが、この人の性情だった。恋愛でもそうであったように、時局の問題にもそうなるらしい。瞼まぶた
の皮が、包みきれないような大きな両眼を剥む
き、こめかみの血管を、膨ふく
れて出して見せるのであった。
むかし、遠藤三郎盛遠であった若年のころ、人妻の袈裟けさ
に恋して、過あやま って、わが恋人の寝首を切り、発心してからもう十年の余、年々、那智の滝に洗われて来たが、まだ、本然の性魂のみは、武者盛遠のままに近い。
悲恋の古傷は、やや癒えかけた。五情を断た
ち、六欲を観じ、熊野道場を始め、南都、比叡の長老にも教えを乞こ
うた。また、大蔵経だいぞうきょう
の経倉きょうそう に一穂すい
の灯を立てて、思念三昧ざんまい
、自己の中の仏性を礼迎らいごう
し、仏果をみがいてきたことでもあった。── けれど、生まれながら人間の本質のとくに強い文覚は、なおまだ、人一倍人間臭い人間であることをどうしようもないらしい。
かくて彼は、自己の生来にも、よくよく、あいそをつかしたが、比叡や園城寺おんじょうじ
や、奈良、熊野などの、既成貴族宗教の内部にも、ほとほと、その腐敗した実状には、あきれ果てていた。そこで、独自の天台新教を、高尾の山奥に創建しようという志を起したのである。
高尾道、栂とが
ノ尾お の山蔭に、鳥羽僧正がむかしいた古庵ふるいおり
が朽ちていた。九条家に乞こ うて、それをもらいうけ、桧皮ひわだ
を葺ふ き足し、柱を起し、近ごろは、居きょ
をそこにおいている。
が、先ごろからの兵乱やら、戦後の非人道的な虐政ぶりなどを見聞みきき
するにつけ、彼は、ぼつ然と、山を下って来た。彼は、実相社会の諸業にたいし、ことに、政治、戦争などの狂潮にむかっては、哲理的な仏智や、心理的な仏光が、無力の近いものであることを知らないほど愚かでもない。しかし地上に、今日ほどな人間堕落を見、骨肉の咬か
み合いを見、塗炭とたん の民を見ながら、おのれひとり山に居て、孤高の庵いおり
に、聖ひじり めかしていることは、出来なかった。性分としても、じっとしていられない彼なのだった。
|