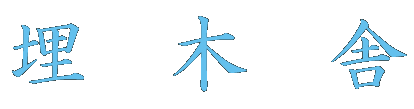やっと、やや泣きじゃくりを収
めた疳持かんもち の子のように、やがて清盛は、はじめ木工助にかい抱いだ
かれて、やしき内の暗い寝室へ入って行った。
「さ。よう、お寝やす
みなされませ。大殿おおどの のてまえは、朝となって、木工助が、よいようにしておきまするので。・・・・お案じのう」
まるで、わが子へするように、木工助は、木枕きまくら
をそこへおいたり、衾ふすま をかぶせて、そしてまた、清盛の寝顔のそばへ、ひざまづいた。
「もう、もう・・・・先ほどのようなお悩みは、ふっつり、夢の中へ、忘れ果てておしまいなされい。たとえ、 真まこと
の父御ててご が、たれであろうと、和子様だけは、まちがいなく、一個の男お
の児こ ではおわさぬか。手も脚も、片輪かたわ
じゃおざらぬ。こころを太々ふとぶと
と、お持ちなされい。天地を父母と思いなされや。のう・・・・それで、よいではござりませぬかや」
「じじ。うるさいよ。・・・・もい去い
ねやい。俺も、考えないで、眠るから」
「おお、さすがは、さすがは、それでじじも安堵あんど
いたしましたわい。・・・・では」
木工助は、もういちど、彼の寝顔へ礼儀をして、あとへ居去いざ
った。そして、室の外から、そろりと帳とばり
を垂れて、立ち去った。
── それから、どれぐらいな時間を、熟睡したことか。
何しろ、寝たとなれば、いつも、正体なしの、清盛だった。
「・・・・兄者人あにじゃびと
。・・・・兄者人」
たれかに、ゆり起こされて、清盛は、しぶい瞼まぶた
を、やっとあけた。小蔀こじとみ
の陽ひ ざしでは、もう午ひる
ちかいように思える。
弟の、経盛であった。
兄のずぼらと違って、公卿の子みたいに、神経質なその弟が、一そう深刻そうな眉まゆ
を近寄せて、さっきから、起こしていたらしいのだ。
「ちょっと、来て下さい。兄者人のことで、また、父上と母上が」
「なに、俺のことで、どうしたって」
「けさほどから、いさかいが始まって、午のお食事も、そっちのけです。いつ果てるとも見えません」
「また、おふたりの夫婦喧嘩げんか
か。・・・・なあんだ、珍しくもない」
清盛は、わざと、不逞ふてい
な大あくびを見せながら、両手を、伸びるだけ突っ張って、いった。
ほっとけやい。めずらしくもない。俺は知らん」
「いけない、いけません兄者人。あなたのことが因もと
ですもの。下の小さい弟たちも、さっきから、お腹が減った減ったと、あのように、泣いてばかりいるし」
「木工助は」
「じじも、さきほど、呼びつけられ、なんだか、母上に、ぎゅうぎゅう、取っちめられている容子ようす
ですよ」
「よしっ・・・・行ってやる」
いきなり、はね起きて、気の小さい弟の眼を嘲あざけ
りながら、清盛は、顎あご の先で。
「俺の、直垂ひたたれ
をよこせ、直垂を」
「着ていらっしゃいますよ。御ふだん着は」
「あ。着たままで、寝ていたのか」
彼は腹帯から、夕べの遣い残りを取り出して、弟の顔のさきは、つきつけた。
「この銭ぜに
で、小さい弟たちへ、何か買って食わせてやれ。若党の平六でも走らせればよい」
「買い食いなどさせたら、あとで母上に、どんなに叱られるか知れません」
「かまわぬ。おれがさせるのだ」
「いくら、兄者人あにじゃびと
の、お言葉でも」
「ばか、惣領そうりょう
だぞ、この平太は。── おれのいいつけも、少しは聞けい。聞いても、いいんだぞ」
弟のひざへ、銭を投げて、清盛の足音は、どすん、どすん、縁を踏み渡って行った。厨くりや
に近い井戸屋根の下もと に立ち、汲み上げた水を、がぼがぼと飲む。そして、顔を洗い、その顔を、布直垂ぬのひたたれ
のきたない袖そで で、こすりこすり、庭を斜めに歩いて行った。
|