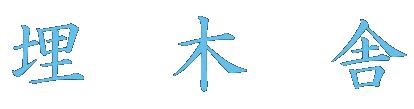| 二三日ばかりありて、月のいみじう明かき夜、端
にゐて見るほどに、 「いかにぞ。月は見たまふや」 とて、 |
| 宮
『わがごとく 思ひは出づや 山の端は
の 月にかけつつ なげく心を』 |
|
| 例よりもをかしきうちに、宮にて月の明かかりしに、人の見けむと思ひ出でらるるほどなりければ、御返し、 |
| 女
『一夜ひとよ 見し 月ぞと思へば
ながむれど 心もゆかず 目は空にして』 |
|
と聞こえて、なほひとりながめゐたるほどに、はかなくて明けぬ。またの夜はおはしましたりけるも、こなたには聞かず。
人々方々かたがた
に住む所なりければ、そなたに来たりける人の車を、 「車はべり。人の来たりけるにこそ」 とおぼしめす。むつかしけれど、さすがに絶えはてむとはおぼさざりければ、御文つかはす。宮
「昨夜よべ は参り来たりとは、聞きたまひけむや。それもえ知りたまはざりしにやと思ふにこそ、いといみじけれ」
とて、 |
| 宮
『松山に 波高しとは 見てしかど 今日のながめは ただならぬかな』 |
|
| とあり。雨降るほどなり。
「あやしかりけることかな。人のそらごとを聞こえたりけるにや」 と思ひて、 |
| 女
『君をこそ 末の松とは 聞きわたれ ひとしなみには たれか越ゆべき』 |
|
| と聞こえつ。宮は、一夜ひとよ
のことをなま心優くおぼされて、久しくのたまはせで、かくぞ、 |
| 宮
『つらしとも また恋しとも さまざまに 思ふことこそ ひまなかりけれ』 |
|
| 御返は聞こゆべきことなきにはあらねど、わざとおぼしめさむもはづかしうて、 |
| 宮
『あふことは とまれかうまれ 歎かじを うらみ絶えせぬ 仲となりなば』 |
|
| とぞ聞こえさする。 |
| 二、三日ほどたって、月のひどく明るい晩、女が縁先近くにすわって月をながめていると、宮から、
「どうしておいでですか。月は御覧になっていますか」 とお手紙があって、 | | 『私と同様に先夜のことを思い出しておいでですか。私は山の端に沈む月を、あなたにお逢い出来ないことになぞらえて、嘆いています』 |
| | いつもより御文が興深く思われるうちに、宮のお邸で月が明るかったあの夜は、だれか人が見なかっただろうかと思い出されるときであったので、ご返事を、 | | 『あの夜宮様と見たのと同じ月だと思いますと思わずながめられますが、私の心は晴れず目はうつろでいるだけです』 |
| | と申し上げて、なおも一人きりでながめているうちに、むなしく夜が明けてしまった。次の夜、宮はおいでになったけれども、女の方では知らなかった。女の家は人々が部屋ごとに住んでいたので、そちらに来た誰かの車を、宮は
「車がある。男がやって来たのだ」 とお思いになる。不愉快だけれど、さすがに女との仲を断ち切ろうとは思われなかったので、女に御文を贈られた。 「昨夜私がお訪ねしたことは、お聞きになりましたか。それさえもご存じないかと思いますと、ひどく悲しいのです」
とお書きになって、 | | 『あなたのおさかんな浮気は承知していましたが、昨夜私が見てしまったことからの物思いは、今日の長雨同様に、ひととおりのものではありません』 |
| | とあった。雨の降っている時であった。女は、
「不思議なことがあったものだ。誰か宮様にこしらえごとを申し上げたのかしら」 と思って、 | | 『宮様こそ浮気なお方と聞きおよんでおります。宮様と同じようには誰が心変わりなどしますものですか』 |
| | と申し上げた。宮は、先夜のことをなんとなく不愉快に思われて、久しくお便りもなかったあとで、こう歌を詠んでこられた。 | | 『恨めしいと思い、また一方恋しいとも思い、あなたのことをさまざまに思って、心の休まる暇とてありません』 |
| | ご返事は、申し上げたいことがないわけではないけれど、それを宮がことさらじみた言い訳にお思いになりそうなも気がひけて、 | | 『お逢いすることはたとえどうなりましょうとも、お逢い出来なくなっても嘆きませんが、二人の仲が恨みの絶えない間柄になりましたなら、嘆かずにはいられません』 |
| | と申し上げた。 |
|