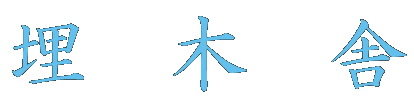かように書き付け、思ひ続けて、涙を拭
ひ、時移 るまでつくづくと候ひて、また、泣く泣く口説
き申しけるは、 「あな、事も愚
かやな。天照大神
四十七世の御末、太上法皇
の第一の御子 、御裳濯川 の御流れ忝
なくおはしまして、代 を治め、国を治めさせたまふ事十九年、一天晴れて、万人
穏やかなりき。されば、誰
の人かこの御位を傾け奉るべきなりしかども、前世
の御果報 の拙
くおはしましけるによって、今かかる変域
の塵土 とならせたまへり。何
ばかりかは都も恋しく思 し
召 され、御怨念
も留 らせおはしましけん。古
厳粧 金屋
の内にては、理世 撫民
の政 を聞
し召 し、百官
相 随
ひ、万国靡 き奉りしかば、長生不老
の門を立て、蓬莱 不死
の薬をのみ求めさせたまひしに、今は雲上
の栄楽 夢のごとし。天災忽
ちに起こりて、九重 の花洛
を出 で、千里
の異域 に遷
らせたまふ。荊棘 を払
ふ人もなし。松の瀝 、span>苔
の露、重なる下に朽 ちさせたまふ、宿執
の程こそ悲しけれ。」 |
| 松山
の 浪 に流れて 来
し舟の やがて空 しく なりにけるかな |
|
| 西行
、夢ともなく、現 ともなく、御返事
申しけり。 |
| よしや君 昔の玉の 床
とても かからん後は 何にかはせん |
|
このように書き付けて、新院のことを偲びながら、涙を拭い、時刻がたつまで、じっと立ち尽くし、また、泣く泣く繰り言して、
「ああ、おろかなことよ。天照太神四十七世の御末、太上法皇の第一の御子、皇統を継ぎ、世を治め、国を治めて十九年、この間、天は雲晴れて、人は皆穏やかであった。だから、この御位を傾ける者が出るなど思いも寄らない事であったが、前世の御果報がつたなくいらしたせいか、今このような辺域の塵土となってしまわれた。どんなにか都を恋しく思われ、御執念を積もらせなさったことだろう。古くは、
厳粧金屋の内で、理世撫民の政をとられ、多くの官僚を従え、国中すべて随順していたから、長生不老の門をたて、蓬莱不死 の薬を求められたのに、今はうって変わって、かっての栄華は夢のようなものである。天災が突然起こって都を出ることになり、千里隔てた異郷にお移りになった。恨みを他州に残し、死を異郷で迎えることになり、歳去り歳来ても、御墓所の荊棘を払う人はいない。松のしずく、苔の露が重なる地下で朽ち果てなさること、前世の執念のなせることとは言いながら悲しい。」 | | 人の寿命とは、松山の浪に流れて漂い来た小舟のようなもの。ともにあっという間に朽ち果ててしまうことよ |
| | 西行は、夢ともなく、うつつともなく、次のような歌を返事としてたてまつった。 | | ええ、ままよ。たとい天皇として権勢ふるまおうとも、死してしまえばそれまでのこと。身の不運を嘆くことなく、安らかにお眠りください |
|
|
| かように申したりければ、御墓
三度まで震動 して恐ろしき。世澆季
に及ぶといへども、万乗
の余薫 はなほ残らせたまひけるにやと、思い遣
るこそめでたけれ。実 に尊霊
もこの詠歌 に御意
解けさせたまひけるにや。さても、彼の蓮誉
は、八重 の潮路
を分けて、宸襟 を存生
の日に訪 らひ奉り、この西行が四国
遍路 を巡見せし、霊魂
を崩御 の後に尋ね奉る。この君御在位の間、恩に浴
し、徳を蒙 る類
、幾 くぞや。されども、今は、なげの情けをかけたてまつる者、誰
か一人 もありし。ただこの蓮誉
・西行 のみ参るべしとは、昔、露もいかでか思
し召 し寄
るべき。 |
| このように申し上げたところ、御墓が感応して三度も震動したのは恐ろしいことであった。末世になろうとも、天皇としての尊厳はなお残っていたのだろうかと思いやるにつけてもめでたい。まことに崇徳院の御霊魂も、この詠歌で得心なさったのだろうか。さて、彼の蓮誉は遠い海路をかき分けて、新院がご生存の時に尋ね来、西行はまた、四国辺地を見歩いた折、新院崩御後のこととて霊魂を弔ったことである。崇徳院がご在位の間、その恩に浴し、徳を蒙った者は数多い。しかし、今となっては、かりそめの情けをかける者さえ一人もいない。この蓮誉と西行だけが尋ねて来ようとは、かつて、新院も想像なさったことはなかろう。
|
|
| 『将門記・陸奥話記・保元物語・平治物語』 発行所:小学館 ヨ
リ |